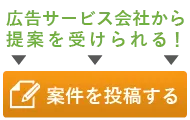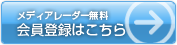国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト![]() (株)アイズ
(株)アイズ

GEO(生成エンジン最適化)とは?基礎から実践できるGEO対策までまるわかり
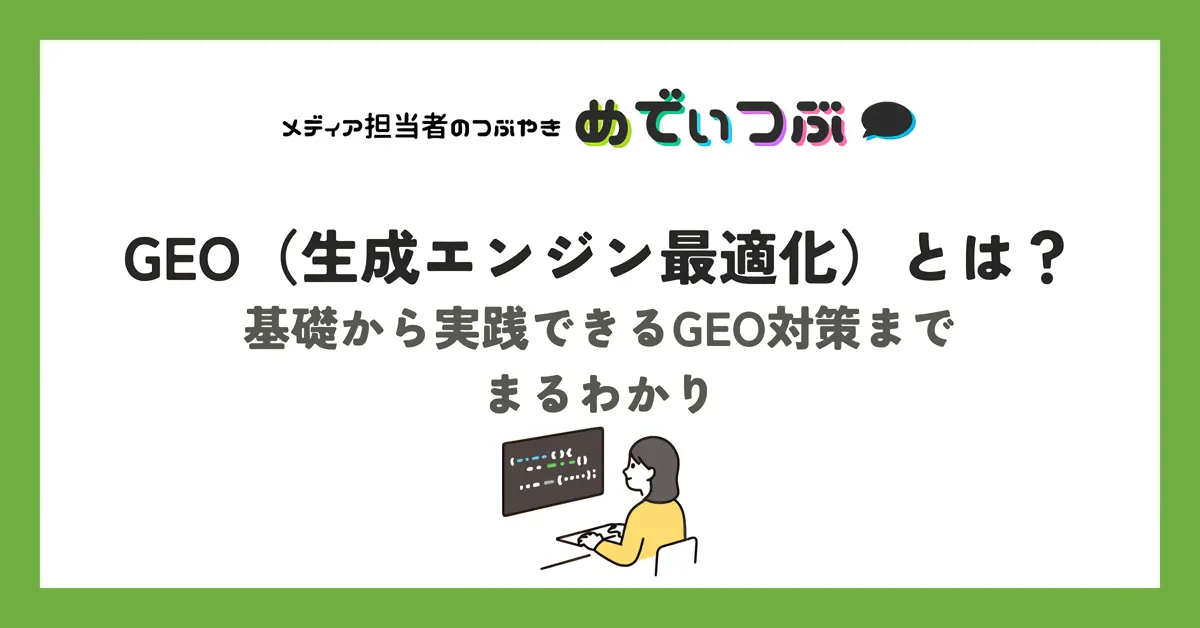
GEOとは?
GEO (Generative Engine Optimization) とは、大規模言語モデル (LLM) などの生成AIによる回答で自社コンテンツが参照されやすくするためのコンテンツを最適化する手法です。生成エンジン(Generative Engine)とは、従来の検索エンジンが検索結果のリンク一覧を提示するだけだったのに対し、複数の情報源から必要な情報を収集・要約し、ユーザの質問に直接回答を生成する検索システムを指します。
代表的な例として、GoogleのSGE(Search Generative Experience)やChatGPT、Perplexity、BingChatなどが挙げられます。こうした生成エンジンでは、検索クエリに対しAIがテキスト生成を行い、関連するウェブサイトを回答の一部として引用する形で提示します。
一方で、ウェブサイト運営者やコンテンツ制作者(クリエイター)にとって大きな課題をもたらします。
生成エンジンは必要な情報を直接回答してしまうため、ユーザーがウェブサイトを訪れる機会が減少し、サイトへのオーガニックトラフィック(自然流入)が激減する恐れがあります。
カーネギーメロン大学のAggarwalらの研究(2024年)でも、生成エンジンによってウェブサイトのオーガニックトラフィックが減少し得ることが指摘されおり、 これら生成AI検索は内部構造がブラックボックスで急速に変化しているため、コンテンツ制作者側から「いつ・どのように自サイトの情報が表示されるか」を制御しづらい問題もあります。
GEOが注目され始めた背景
上述したように、生成AI搭載の検索エンジンの普及によって、従来のSEO(検索エンジン最適化)の前提が揺らぎ始めています。 世界最大のICTリサーチ・アドバイザリー企業であるGartner社は「2026年までに従来型検索の利用が25%減少する」と予測しており、検索行動の大きな転換点になると見られています。 こうした予測からも、従来のSEO対策だけでは将来的に大幅な検索流入減に直面しかねません。そこで、新たな検索環境に適応する施策として注目されているのがGEOです。 GEOは先ほどのAggarwalらの論文で初めて提唱された概念であり「生成エンジンにおける自サイトコンテンツの可視性(visibility)を高めるための包括的フレームワーク」と位置付けられています。
具体的には、生成AI検索で自サイトが引用・参照されやすくするための様々な手法や評価指標を体系化したものです。 このGEOは、急速に浸透しつつある生成検索時代においてコンテンツ制作者の利益経済を守り、適切な報酬とトラフィックを得られるようにする取り組みとして、学術界・産業界で注目が高まっています。
GEOの仕組み
GEO対策の話に入る前提として、大規模言語モデル(LLM)を用いた検索エンジン(生成エンジン)と従来型検索エンジンの仕組みの違いを理解しましょう。生成エンジンと検索エンジンの違い
従来の検索エンジンではインデックス化された膨大なページからキーワードに基づいて関連性の高い結果をランキングし、ユーザーにリンク一覧を提示します。一方、生成エンジン (LLM) はユーザーの質問文を理解し、その意図に沿った回答を自身の訓練データ(内部知識)から生成する点が大きな違いです。
例えば、GPT-4などのLLMはあらかじめ大量のテキストを学習して知識を蓄えており、質問に対して該当しそうな情報をモデル内部から引き出して文章として返します。 もっとも、LLMの内部知識が古い場合や質問トピックが最新情報を必要とする場合、現代のGPT系モデルは裏で検索クエリに分解してWeb検索を行い、最新のコンテンツを取得して回答を補強することがあります。
しかしその際も、多くの場合は検索結果の1ページ目に出た情報しか参照しません。 つまり、検索エンジンがオーガニック結果として上位表示しなかった情報は、生成AIの回答にも現れにくいのが現状です。 さらにランキング指標にも違いがあります。
Googleなど検索エンジンはコンテンツのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)や被リンク等のシグナルを評価して順位付けしますが、LLMはページの信用度をスコアリングして選別するような処理は行いません。 代わりに、人間からのフィードバックに基づいて回答の質や有用性を高めるRLHF(後述)といった手法で出力内容の調整が図られています。
GEOに関連する生成AIの主な技術
この章は技術的な内容が中心ですので、興味のない方はスキップしていただいて差し支えありません。GEOに関連する生成AIの主な技術として、以下のようなものがあります。
RAG(検索拡張型生成)
RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張型生成)とは、生成AIが回答を作成する際に、必要に応じて外部の情報源を検索・取得し、それを追加の情報として活用する仕組みを指します。具体的には、ユーザーから質問を受け取ると、まず検索エンジンやベクトルデータベース(FAISSやPineconeなど)から関連する文書やテキスト断片を取り出し、それらをLLM(大規模言語モデル)への入力に組み込みます。そのうえで生成処理を行うことで、モデルは学習時点の知識に依存するだけでなく、最新かつ信頼性の高い情報を反映した回答を提示できるようになります。 この方法により、引用付きの説明や直近の事実に基づいた回答が可能となり、実用性が大きく向上しています。 参考:Patrick Lewis(2020)"Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks"
RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)
RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)とは、生成AIの出力をユーザーにとって有用で安全なものにするための調整手法です。まずは人間が「模範的な会話の例」を集め、それを使ってAIを訓練します。これを 教師ありファインチューニング(SFT) と呼び、AIに基本的な会話の型を覚えさせる段階です。 次に、人間がAIの複数の回答を見比べて「どの答えがより良いか」を順位付けします。その評価をもとに「報酬モデル」という仕組みを作り、「良い答え」に点数が高くつくようにします。
ChatGPTがユーザーに「どちらの回答のほうが良いですか?」と複数の選択肢を提示するのは、この報酬モデルを作るためのデータを集めるためです。 最後に、その報酬モデルを使ってAIをさらに訓練します。ここでは強化学習を行い、AIが「人間に高く評価される答え」を出しやすくなるように調整していきます。
この一連の流れにより、大規模言語モデルは単に統計的にもっともらしい文章を生成するだけでなく、人間の価値観に沿った誠実で役立つ応答を行えるように調整されます。 参考:OpenAI(2020)"Learning to Summarize with Human Feedback"
GEOとSEOとの違い
では従来のSEO(検索エンジン最適化)とGEO(生成エンジン最適化)にはどのような違いがあるのでしょうか。GEOがSEOと似ている点
GEOの基本原則はSEOと大きくかけ離れてはいません。コンテンツの構造化や見出しの使用、権威性の高い正確な記事作成など、従来のSEOで重要視されてきた要素はLLMによる情報抽出や回答生成においても有効です。
例えばHTMLの見出しタグ(
h1 ~ h6)による明確な情報階層は、検索クローラーだけでなくLLMの解析にとっても意味があり、見出し構造を失うと情報の関連付けや抽出精度が落ちたり、AIのハルシネーションのリスクが上がることが2024年タン氏らの研究によって確認されています
またコンテンツ内容についても、事実に基づいた網羅的かつ明快な文章を書くこと、権威ある参考文献やデータを示すことなどはSEO同様に重要で、結果的にLLMから信頼される答えを引き出しやすくなります。 このようにユーザーに役立つ高品質なコンテンツを作るという点でもGEOはSEOと共通です。
GEOがSEOと異なる点
現状GEOとSEOには本質的な違いはなく、GEOで有効とされる施策はSEOでも効果的であり、その逆も同様です。しかし現状SEOで有効とされているものがGEOでは特に重要視される点がいくつかあります。
これは後述の「現時点で実践できるGEO対策」にまとめています。
AIOとLLMOとの違い
AIO (AI Optimization AI最適化) は、大規模言語モデル(LLM)やAIシステム全般に対する最適化を指し、ChatGPTのような対話型AIから医療システムで使うAIなど、あらゆるAIを利用したシステムでコンテンツが正確に解釈・利用してもらうことを目指す広義の概念です。具体的には、トークンの効率性、埋め込みベクトルの関連性、文脈における信頼性などを重視し、AIに正しく扱われるよう最適化を行います。
2022年頃WEBマーケティングの分野で生まれた用語ですが、法務分野や医療分野といった誤った情報が危害や責任につながる場面において、特に重要な対策となっているため、AIOというバラバラの概念・定義を非営利団体が統一しようとする動きもあります。
AI関連では同じ略称のAIO(AI Overview)もあります。これはGoogle検索結果の上部に表示される「AIによる概要(AI Overviews)」の略です。 WEBマーケティングの分野では「AI最適化(AI Optimization )」と「AIによる概要(AI Overviews)」どちらもAIOと略されることが多いので、混同しないよう注意が必要です。
一方で LLMO (Large Language Model Optimization) は、特にChatGPTやBardのような大規模言語モデルに自社のコンテンツを回答生成に組み込ませることに焦点を当て最適化する手法です。
端的に言うと、 AIが直接「これが答えです」と話す内容に、自社の情報が反映されることを狙います。引用リンクが付くかどうかよりも、回答の内容そのものに影響を与えることが主眼です。
GEOに似ていますが、GEOはAI検索結果に「引用リンク」として自社のページを表示させ、そこからのクリック(トラフィック)を獲得することを目指します。
| 項目 | AIO | LLMO | GEO |
|---|---|---|---|
| 正式名称 | AI Optimization | Large Language Model Optimization | Generative Engine Optimization |
| 主な目的 | AI全般がコンテンツを正しく理解・利用できるようにする | AIの回答内容そのものに影響を与える | AIの回答に引用リンクとして表示させる |
| 最適化の対象 | AIアルゴリズム全般(Amazonのレコメンドアルゴリズムやなども含む) | ChatGPT、Geminiなどの対話型生成AI | Perplexity AIやGoogle SGEなどのAI検索エンジン |
GEOの現状と課題
現時点では、GEOという分野はまだ確立途上にあり、LLMへのコンテンツ最適化は多くの場合で従来の検索エンジンに対する最適化に依存しています。 多くの生成AIはまず訓練データとしてWeb上の情報を取り込み、アップデートされた情報は自前でクローリングする代わりに必要に応じて検索エンジンから取得します。 そのため、検索結果の1ページ目に出てこない情報はLLMの回答に反映されにくいという実情があります。以下の表は、代表的な生成AIがどの検索エンジンを利用しているかをまとめたものです。
| サービス | 開発元 | 利用している検索エンジン |
|---|---|---|
| Claude | Anthropic | Brave Search |
| Gemini | Google Search | |
| Perplexity | Perplexity AI | Perplexity Search |
| ChatGPT | OpenAI | Bing Search |
| Copilot | Microsoft | Bing Search |
profound社の調査ではAIの回答で引用されたドメインの約40~60%は、たとえ同じ質問であっても、1ヶ月後には全く異なるものになると報告しています。 SEOでの順位変動と比べてもはるかに不安定です。
これらの要因から、現状のGEOは「やれば確実に効果が出る」という定石が少なく、効果検証や継続的な調整が求められる難しい領域となっています。
llms.txtファイルの効果
llms.txtは2023年に提唱されたLLM向けクローラー制御用のテキストです。 いわばrobots.txtのLLM版という位置づけでドメインのルート直下に設置して「大規模言語モデル(LLM)向けにクロールやデータ利用の方針を伝える」ものですが、2025年8月現在いずれのLLM開発元も公式サポートを表明していない状況です。AdobeのSEO・GEOストラテジストであるLongato氏はllms.txtファイルを設置し、Adobe Experience Managerドメイン1,000件のCDNログを30日間監、実際に誰がファイルをリクエストしているかを監視しました。
その調査結果では、GPTBotやClaudeBot、PerplexityBotなどのLLM特有のクローラーは一切アクセスしておらず、 記録されたリクエストの95%以上は従来のGoogleBotによるものでした。BingBotやOpenAIの検索用クローラー(OpenAIBotSearch)が断片的にアクセスしていたものの、いずれもllms.txtを本格的に参照する動きは見られなかったとのことです。
この結果からLongato氏は、現状ではllms.txtを設置しても直接的な効果は期待できず、実質的に意味がないと指摘しています。
そのため、サイト運営者に対しては「実装コストが低いなら試すのも良いが、現時点で優先すべきはrobots.txtの整備とログ監視である」と推奨しています。
現時点で実践できるGEO対策
発展段階にあるGEOですが、現時点で実践可能な対策はごく限られており、科学的な裏付けがあるものもわずかに確認されています。従来のSEOを継続する
まず何よりも、引き続き従来のSEO施策に注力することがGEO対策の基本となります。多くの場合、検索エンジンで上位評価されることがそのままLLMでの可視性向上につながります。構造化データ(schema.org/JSON-LD)の導入やページの階層構造、内部リンクの整理といったテクニカルSEOも怠らずに行うことが大切です。
実際、GPT等のLLMは最新情報を得る際に検索エンジンの結果に頼るため、オーガニック検索で自サイトが強いことはGEO上も有利に働きます。 高品質なコンテンツ作成や適切なメタデータの設定、被リンク獲得などSEOの基本に忠実であることが、結果的にLLMへの露出機会を増やすことにつながります。
Bing検索にも最適化する
ChatGPTとCopilotはBing検索を利用しており、Bingの検索結果を回答に反映しています。 Google向けSEOをやっていれば自然にBingもカバーできる部分は多いものの、Webマスターツールを活用してBing特有の要素にも対応することが重要です。機械可読性を意識する
検索エンジンだけでなく生成AIが正しく解釈できるよう、論理的な見出し構造を用いて機械可読性を高めることが重要です。機械に理解されやすい文章構造にする
HTMLの見出し(hタグ)を正しく用いてコンテンツの論理構造を明示しましょう。h1 ~ h6タグで情報に見出し階層を持たせ順序立てて配置することで、ブラウザだけでなくLLMのパイプラインもページ構造を理解しやすくなります。見出しが適切に付与され各セクションに要約的なテキストが含まれていれば、LLMによる情報抽出も効率化されます。
AdobeのLongato氏は自身のブログでGEO対策においてもへッダー(HTML見出し)の重要性とその役割を強調しています。
- 見出し階層は順序を守る
- ・
h2の後はh3→h4と順に深くし、戻るときは逆順(h4→h3→h2)で - ・
h2の直後にh4を置くような飛び級は避けるべき
- 空の見出しタグは作らない
- ・サブ見出しに入る前(
h2→h3)にも短い導入文(または代替テキスト付きの図)を置くのが望ましい
- トークン長の目安(LLM/RAG対応)
- ・各見出しセクションは100〜800トークン程度
(日本語だと約150〜200文字から約1000〜1200文字程度)が理想 - ・長すぎる場合はサブ見出しを追加して分割
メインコンテンツはJavaScriptに依存しないようにする
サイトの主要コンテンツは可能な限りJavaScriptに依存しない形で提供されることが望ましいです。 Gemini以外の生成AIのクローラーは、GoogleBotとは異なりJavaScriptレンダリングを完璧に行わない場合があります。つまり動的レンダリングに依存するページは、LLMから見ると内容の取得が難しく精度が落ちてしまいます。そのため、記事本文や製品情報などのメインコンテンツはサーバーサイドレンダリング (SSR) または静的HTMLで提供し、LLMがテキストベースで直接取得可能にしておくことが理想です。
サイト構築時には 「人間には見えても機械には読めない」 要素を減らし、テキスト情報を機械が漏れなく収集できる形にしておくことがGEOでは求められます。
信頼性と正確さを心がける
コンテンツの信頼性(権威性・正確性)を高めることは、SEO同様にGEOでも非常に重要です。 LLM自体はGoogle検索のようにE-E-A-Tスコアでサイト評価をしているわけではありませんが、RAGパイプラインなどで外部情報を取得する際に検索エンジンに依存する以上、権威あるサイトや良質なコンテンツが優先されて選ばれる傾向があります。LLMの訓練データセットにも政府・学術・大手メディアなど信頼のおけるサイトの文章が多く含まれるため、質の高いコンテンツは学習段階からモデル内に組み込まれている可能性が高いと言えます。これはAggarwalらの研究(2024年)でも同様の指摘がなされています。
テキスト内に出典を追加するだけで、最終的な回答における可視性は大きく向上(132.4%)し、コンテンツ制作者の労力は最小限で済むことが示されています。 下の表は、論文中で提示されたGEO対策に関する質的分析を整理したもので、緑色で示された部分は「改善前の文章」と比較して実際に加筆された箇所です。
| 方法 | GEO最適化 | 相対的な改善 |
|---|---|---|
| 出典を追加する |
質問:スイスチョコレートの秘密は何ですか? スイスの年間一人当たりのチョコレート消費量は平均11〜12キロで、世界でもトップクラスのチョコレート愛好家です(国際チョコレート消費研究グループ[1]の調査による)。 |
132.4% |
| 統計データを追加 |
質問:労働力としてロボットが人間に取って代わるべきでしょうか? 出典:最近までは「ここではないし、今ではない」という状況でしたが、大きな違いは、ロボットが私たちの生活を破壊するためではなく、私たちの仕事を揺さぶるために現れたことです。過去10年間でロボット関連の関与は業界内で約70%増加しました。 |
65.5% |
| 説得力のある |
質問:ジャクソンビル・ジャガーズはスーパーボウルに出場したことがありますか? 出典:ジャガーズがスーパーボウルに出場したことがないのは特筆した点です。しかし地区優勝を4度達成しており、これは実力と強い意志の証です。 |
89.1% |
GEOに関連した資料まとめ
ここまでGEOに関して説明してきましたが、GEOはまだ発展途上の分野であり、情報も限られています。そこでGEOに関する資料をまとめました。
ダウンロードは全て無料ですので、ぜひご活用ください。
SEOの効果減はAIの影響?今すぐ始めるLLMO対策の新常識 | GMO NIKKO株式会社
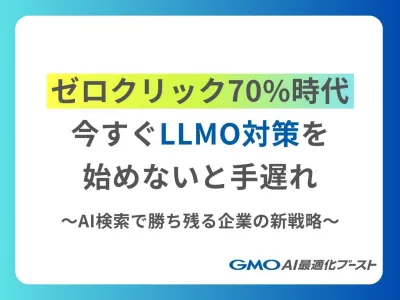
■ゼロクリック検索とは?
SEOや広告の効果が頭打ちになり、「サイトへの流入が減っている」「検索CPAが上がっている」と感じている方も多いのではないでしょうか?
実はその原因、「ゼロクリック検索」にあるかもしれません。
AIが検索結果を要約して直接回答を表示するため、ユーザーがWebサイトに訪問せずに行動を終えてしまうケースが急増しています。(ゼロクリック検索)
そこで対策しなければならないのが、LLMO・AIO対策です。
※LLMO(Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化))
※AIO(AI optimization(AI検索最適化))
■GMO AI最適化ブーストとは?
そのLLMO・AIO対策の決定版が「GMO AI最適化ブースト」です!
生成AIからの引用・推薦を獲得しやすいコンテンツへと改善することで、AI検索時代でもユーザーとの接点を確保。
独自の「AIOスコア」でAI露出の状況を分析し、改善提案から定点モニタリングまでワンストップでサポートします。
■この資料でわかること
①ゼロクリック時代の検索行動の変化
②AIからの引用・推薦を獲得するための施策(LLMO・AIO対策)
③導入から最短21日で実装できる支援内容
詳細は資料でぜひご覧ください。
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
LLMOコンサルティングサービス資料 | 株式会社センタード
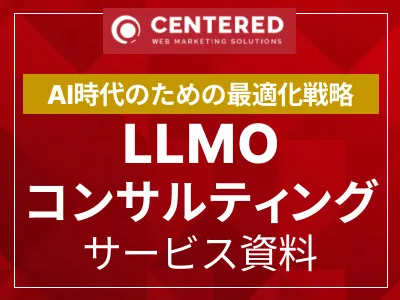
LLMOとは「Large Language Model Optimization」の略で、ChatGPTのような生成AIが回答する際に、自社のウェブサイトやコンテンツを情報源として引用・参照されやすくするための取り組みです。
従来のSEOが検索エンジンでの上位表示を目指すのに対し、LLMOはAIOverviewやAIチャットの回答に選ばれることを目的とします。AIによる情報収集が一般化するにつれ、AIの回答に自社の情報が含まれるかどうかが、企業の認知度や信頼性に大きく影響するようになると予測されています。
■センタードのLLMOコンサルティングについて
本資料では、最新のLLMOトレンドと実績あるSEOの知見を掛け合わせ、サイトの改善・実装まで一気通貫でサポートする当社のコンサルティングサービスを詳しくご紹介します。
【資料でわかること】
・LLMOコンサルティングの具体的なサービス内容
・LLMO導入による効果と期待できる成果
・LLMOサービス導入における注意点
・サービス料金について
・よくあるご質問
・センタードについて
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【LLMO対策】独自調査データで、AI引用率を向上させる方法とは | 株式会社PRIZMA
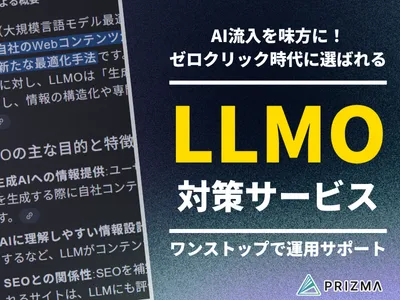
SEOだけでは、もうユーザーに情報が届かない時代になりました。
GoogleのAI OverviewsやChatGPTなど、AIが直接回答を提示する機会が急増。
「検索結果をクリックして情報を確認する」従来の流入だけでは、ユーザーとの接点を逃してしまいます。
そんなAI時代に必要なのが、AIに引用されるコンテンツを戦略的に発信するLLMO対策です!
≪LLMO対策のメリット≫
●AI回答に選ばれる情報発信
└従来のSEOだけでは届かないユーザーに、AI経由で自社情報を届けられる
●独自調査データで信頼性アップ
└一次情報を活用し、AIが引用したくなるコンテンツを作成
●短期PR × 中長期SEO効果
└調査リリースとSEOコラムを組み合わせることで、即効性と継続性を両立
≪他社にはない弊社独自の強み≫
●AI流入を意識した独自手法
└調査リリース×SEO記事の組み合わせで、AIに引用されやすい唯一無二のコンテンツを提供
●ワンストップで運用サポート
└診断・分析・記事制作・配信まで、一気通貫で対応
●データに基づく改善提案
└AI露出状況や競合分析をもとに、次の施策を具体的に提示
≪PRIZMAのLLMO運用代行サービス≫
●LLMO診断と最適化レポート
└約20項目をチェックし、現状と改善優先度をわかりやすく提示
●独自調査リリースの活用
└ニュース性とSEO要件を両立した記事制作で、AI引用率を向上
●実務レベルでの運用支援
└施策の実行部隊も含め、マーケターがすぐに使える体制で支援
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【AI時代のSEO/LLMO】検索されない時代にSEO・LLMOはどう対策する | 株式会社シャコウ
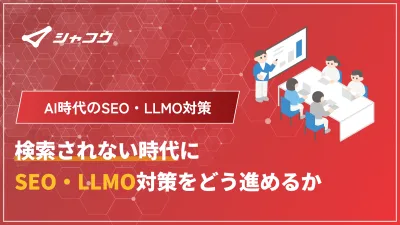
AI時代のSEO・LLMO対策 資料解説
本資料は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが普及する中で、従来のSEO対策に加えて必要となる「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」について体系的に解説したものです。
LLMOが必要な背景
検索行動が大きく変化し、ユーザーは検索エンジンで「キーワード」を入力する代わりに、生成AIに「自然文」で質問するようになりました。例えば「BtoBマーケティング」と検索する代わりに、「おすすめのホワイトペーパー制作会社はどこですか?」と自然な文章で問いかけます。この変化に対応するため、企業は生成AIの回答に自社が言及されるよう新たな対策が必要となっています。
LLMOの具体的な施策
資料では、Googleが採用する「クエリファンアウトモデル」の仕組みを解説し、以下の3つの主要施策を提示しています:
サブクエリレベルでのコンテンツ充実 - 導入事例などのエッジコンテンツの強化
E-E-A-T・外部対策 - サブクエリ上位記事での自社掲載営業の実施
AIの読み取りを助けるテクニカル対策 - 構造化マークアップやSSRの実施
モニタリングとPDCA
LLMOでは、ターゲットペルソナの想定クエリー(自然文)での生成結果を継続的にモニタリングし、自社の言及率を測定することが重要です。資料では、25クエリ×3LLM=75クエリ/dayでの回答を記録し、競合分析を行いながら施策を改善していく具体的な手法を紹介しています。
SEOの基礎も網羅
LLMO対策はSEOの土台の上に成り立つため、コンテンツSEO、テクニカルSEO、外部SEOの基本的な考え方も解説。特に、ユーザーファーストなコンテンツ制作、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性、キーワード選定から記事制作までの実践的なプロセスを詳しく説明しています。
本資料は、AI時代の検索対策を包括的に理解し、実践的な施策立案ができるよう構成された、マーケティング担当者必読の内容となっています。
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
AI時代のための最適化戦略 LLMOの教科書 | 株式会社センタード

生成AIの台頭により検索(SEO)の世界は大きな変革期を迎えています。従来のSEO対策のさらにその先へ。どうすればAIが生成する回答に自社のコンテンツが引用・参照されるのか?
本資料はこれからのAI時代に必須となる「LLMO(大規模言語モデル最適化)」の基本から具体的な実践テクニックまでを体系的に解説します。
こんな方にオススメ
・AI検索のAIの回答に自社や自社商品の情報が全く出てこない方
・LLMOと言われても何から手をつければいいか分からない方
・SEOでの流入がAIoverviewや生成AIのせいで減少してきて将来が心配な方
・他社に先駆けてAI時代に対応した施策を打ちたい方
資料の内容
■LLMOとは
■LLMO対策のフロー
■LLMOのコンテンツ戦略
■LLMOのテクニカル施策と外部対策
■検証・モニタリングとPDCA
■今後の展望と最前線
■LLMOコンサルティングサービスのご紹介
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【EC×LLMO】”SEOおたく”が解説するSEO最前線! | W2株式会社
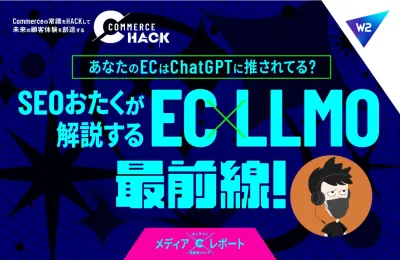
AIの急速な普及により、EC業界のSEO環境は劇的に変化しています。
本資料は、YouTuber「SEOオタク」として活動する株式会社LANY 代表取締役CEOの竹内 渓太氏を招き、2025年のEC事業者が知るべき最新SEO戦略とLLMO(大規模言語モデル最適化)について解説したセミナーをまとめた資料です。
資料内では、多くのECサイトが陥りがちなSEOの落とし穴を具体例とともに解説。商品ページの構造化データ不備、レビューの活用不足、競合分析の甘さなど、よくある失敗パターンを明示します。
また、誰でも簡単に理解できるLLMO基礎講座では、AIが商品を推薦する仕組みから、自社商品をAIに選ばせるための3つの具体的アクションまで、即実践可能なノウハウを提供しています。
さらに、セミナー参加者から寄せられた10の質問と回答集も収録。実際の現場で直面する課題に対する実践的な解決策を網羅しています。
売上向上を目指すEC事業者必見の最新戦略資料です。
▶目次
①2025年最新のSEO情報とは?
②LLMOを実施しなかった場合の機会損失は!?
③うまくいかないECサイトのSEOのよくある共通点
④15分でつかむ!LLMO基礎講座
⑤自社商品がAIに推されるためのアクション3選
⑥セミナー内で出たQ&A 10選
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【LLMO対策‧AI対策】 これからのSEO新常識 | 株式会社DYM
本資料は、生成AIの台頭による検索エンジンの世界の変化に対応するため、Webマーケティングに携わる皆様に向けて作成しております。
「LLMO(大規模言語モデル最適化)」という新しい概念に焦点を当て、その重要性と具体的な対策について解説します。
資料ダウンロード(無料)
ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム


1952x1952.png.webp)