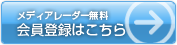国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト


公開日:2023年05月31日 更新日:2023年08月23日
地方創生とは?地域活性化との違いや広告手法・成功事例を紹介!
 地方創生とは?地域活性化との違いや広告手法、成功事例を紹介!
地方創生とは?地域活性化との違いや広告手法、成功事例を紹介! 地方創生とは
地方創生とは、都心と地方の格差をなくし、それぞれの地域で住みやすい環境をつくることで活力のある日本社会の維持・実現を行うことです。 少子高齢化が進むことにより労働人口が減り、都市部へ労働力が集中して経済力に格差が生まれている状況をなくし、日本全体で国力を上げることを目的としています。 地元で暮らすことや働くことへの不安を減らし、安心して生活ができるように地域経済が自走できる仕組みづくりに取り組んでいます。参考:地方創生とは?:財務省北陸財務局
地域活性化との違い
地方創生が地方での環境を整え、少子高齢化による人口の格差をなくすことに対し、地域活性化は地方創生の効果により地域を活気づかせることです。 地方への移住や地域イベントの開催により、住民が増えたり税収が上がったりして、地域に活気が生まれることを地域活性化といいます。 そのため、地域活性化とは地方創生の結果と考えると良いでしょう。地方創生に役立つ広告媒体資料一覧
地方創生に役立つ資料を下記にまとめています。 資料は無料でダウンロードできるので、是非お役立てください!【自治体様向け】新型PR活動で地方創生へ!旅行観光を促進するプロモーションガイド | 株式会社ドワンゴ

【地方創生:eeeコトを発信】創美社ライブ配信サービス | 株式会社創美社
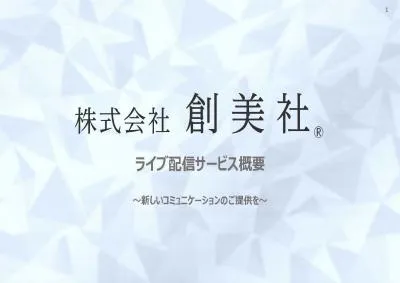
【地方創生・自治体PR担当者様必見!】地方PR動画の考え方・作り方 | 株式会社エレファントストーン
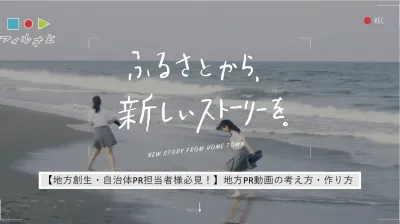
地元「食」で地方創生!日本版DMO向けスキームのご案内 | 株式会社ほっとこうち
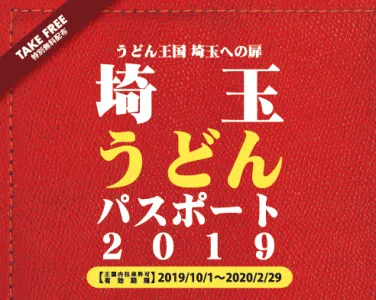
地元タウン情報誌発行社だからできる地方創生事例集 | 株式会社タウン情報全国ネットワーク

【ネイティブ.メディア】地域や自治体の移住促進・関係人口創出・地方創生の情報発信 | 面白法人カヤック

地方創生に向けたSNS活用方法!誘客・ファン獲得のアイデアと各事例をご紹介! | ラグナロク株式会社
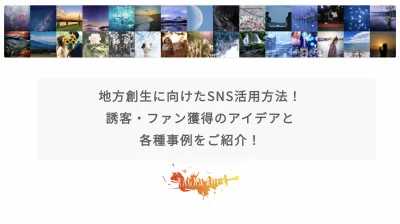
旅行・地方創生PR特化型ソーシャルメディア動画配信パッケージCreatorsTV | 株式会社BitStar
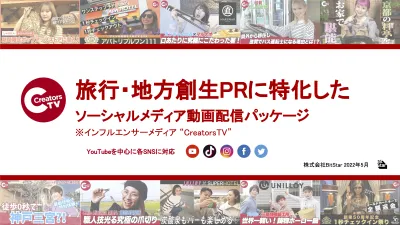
日本全国を網羅するメディアネットワークによる地方創生プロモーション【共同通信社】 | 株式会社共同通信社
【遊びで地方創生】自治体様・観光協会様向け!モデルコース開発・情報発信者育成 | プレイライフ株式会社

地方創生を取り入れるメリット
地方創生を取り入れることは、少子高齢化による人口の現象だけでなくさまざまなメリットがあります。 ここでは、地方創生を取り入れることによって得られるメリットを下記の4つに分けて紹介します。よりよい地域環境を目指すためにも、地方創生のメリットについて確認していきましょう。新しい観光資源の発掘と活性化
観光資源の定義は広く、山や洞窟などの自然のものからテーマパークや史跡などの人工物までさまざまです。 地方創生により外部の人間の目線や意見を取り入れることで、新たな観光資源の発掘や開発につながる可能性があります。 以前からあるものでも、PRの方法が変わることで注目を集めるかもしれません。 新しいものを発掘することで、地域の活性化を期待することができるでしょう。人口減少の克服
地方創生により地方への移住や定住を進めることや子どもが安心して暮らせる町づくりをすることで、減少していく人口の克服が可能です。 少子高齢化社会で不安視されるのは、若者が都心へ出てしまうことで高齢者が地方に取り残されていくことです。 安心して住みやすい環境づくりを進めることにより、若者の地元離れや都心に人口が集中する事態を避けることにつながります。自治体や地元民からの支援・理解を得られやすい
地元の過疎化が進むと、就職先がなくなることや若い人手が減ることなど不便になることが増えます。 そのため、自治体や地元民は地域を活性化することに対して理解がある人が多く、どうにか地域の活性化を行いたい自治体からは支援を得られやすいことが考えられます。地方企業との差別化を図れる
経験が豊富な大手企業は、マーケティング力を活かして地元企業との差別化を図る戦略が可能です。 地域をブランド化して展開していくうえで、どういった魅せ方をするべきか、どの部分が収益化につながるかなどを分析してプラン作成できます。地方創生の取り組み手法
地方創生には企業だけでなく、個人で取り組むことも可能です。 ここでは、地方創生に取り組むための手法を下記の3つに分けて紹介します。知ることで地方創生への参加を検討する機会になるので、参考にしてください。地域おこし協力隊
地域おこし協力隊とは、都市から過疎地域へ住民票を異動し、1〜3年の任期で自治体が求める支援活動を行い、地域への定住や定着を図る取り組みのことです。 地域ブランドを用いた開発・販売・PRや農林水産業への従事を行うなど、活動はさまざまです。参考:総務省|地域力の創造・地方の再生|地域おこし協力隊
Uターン企業
地方創生における「Uターン」とは、地方から都市へ移住した人が生まれ育った地方に戻り働くことです。 他にも、もともと都市で育った人が地方に移住する「Iターン」地方で育った人が都市に出て、育った周辺の地方都市に移住して働く「Jターン」などがあります。 テレワークの普及やコロナによる人口密度の高い場所を避ける考え方から、地元での就職や転職を検討する若者が増加傾向にあります。自治体SDGs
自治体SDGsとは、SDGsの考え方である「持続可能な目標」や「誰一人取り残さない社会」を実現するために自治体の活動より地方創生を推進することです。 地域の問題を洗い出し、解決方法を模索し地域の住民と協力して取り組んでいくことで、地方の活性化につながります。 また、問題を解決することで地域住民の生活の質を向上することができます。地方創生の成功事例
地方創生は自治体や企業などにより、実際にさまざまな形で行われています。 ここでは地方創生の成功事例として、下記の5つの項目に分けて紹介します。地域とのつながりを強固にし、将来を見据えたサービスを活用することで、住みやすい地域環境を整えるための参考にしてください。内閣官房・内閣府総合サイト 地域創生
内閣官房・内閣府総合サイト 地域創生では、実際に行われた地方創生の事例を見ることが可能です。 市町村別に内容を確認することもできるので、自分が行ったことがある場所や住んでいる場所がどのような施策を行ったのか調べてみるのも良いでしょう。 また、これから地方創生に関わりたいと考えている人にも参考ポイントなど詳細が記載されているためおすすめします。参考:地方創生関連事例|内閣官房・内閣府総合サイト 地域創生
地元の元気プロジェクト 明治安田生命
生命保険会社で有名な明治安田生命は「地方創生の推進」に貢献すべく「地元の元気プロジェクト」を行っています。 地元の元気プロジェクトとは、自治体との連携や地域でのイベント開催により、暮らしやすく人々が繋がり支え合える地域社会を目指す取り組みのことです。 具体的には、道の駅で健康増進のためのイベントを行ったり、Jリーグや地元Jクラブと協働したウォーキングのイベントを開催したりしています。現在は全国で連携協定を結んだ自治体数は※911自治体、イベント開催時に参加した参加者数はのべ※660万人と今後の発展に更に期待がもてます。 (※2023年3月末時点)
参考:明治安田生命の「地元の元気プロジェクト」が大臣表彰
夜間オンコール代行™サービス ドクターメイト株式会社
ドクターメイト株式会社は、オンラインでの医療相談や「夜間オンコール代行™」などにより介護施設を24時間365日サポートする会社です。 「地方創生SDGs国際フォーラム2023」にてドクターメイト株式会社は、福岡県北九州市と共に取り組んだ実証事業が優良事例選定証を受賞しました。 優良事例として選定された「夜間オンコール代行™」サービスは、負担となる夜間オンコール業務を外部委託することで日常業務の負担を軽減することが目的です。実証事業を行った結果、活用後のアンケートでは夜間オンコール代行サービスは有効に感じるといった回答が76.8%という結果になりました。 今後、高齢化社会により必要となる介護職への負担軽減を実現することで、介護人材の確保が期待できます。
参考:内閣府 地方創生SDGs官民連携優良事例に選定
やまがた出産・子育てアプリ 母子モ株式会社
母子モ株式会社は、アプリやデジタルサービスなどのICTを取り入れた子育て支援を行っている企業です。 子育て支援は、アプリを使った予防接種のスケジュール管理や自治体への子育て関連事業のオンライン化支援も行っています。 だれもが安心して子育てができる町を基本理念として掲げる山形市では、子育て世代が安心して使える便利なアプリ「やまがた出産・子育てアプリ」を導入しました。アプリの導入は母子モ株式会社の子育て関連事業のオンライン化支援により実現され、自治体の制度やサービス案内などの地域と密接した情報の提供を可能にしました。 これにより、子育ての悩みを軽減し、自治体から提供されるさまざまな制度やサービスに関する案内を受け取りやすい環境づくりに期待できます。
参考:母子手帳アプリ『母子モ』が山形県山形市で提供を開始!
まとめ
地方創生は、活力のある日本社会を実現し維持していくために、都市部と地方との格差をなくす活動のことです。 地方創生を行い、地方に活気がみなぎることで地方活性化へとつながります。 地方創生のメリットには、人口減少を克服する他にも新たな観光支援の発掘や地方企業と差別化を図れることが挙げられます。実際に地方創生を行い、成功した企業の事例などを見ることで、地方創生に興味を持ち、今後新たな視点で取り組むことができるかもしれません。地方創生を理解し、日本の将来をよりよいものに変えていきましょう。
ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム
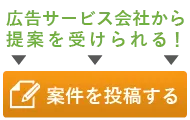

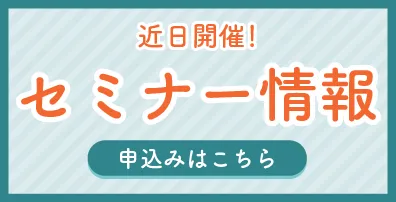
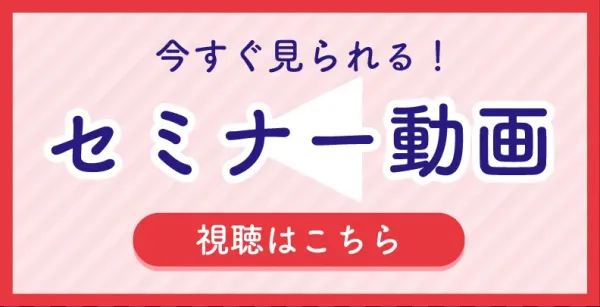
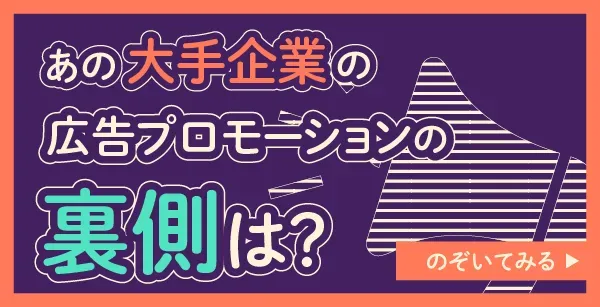
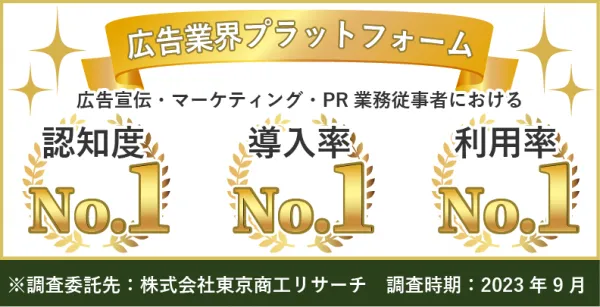
_396x250.png.webp)

- Pontaのリアル購買・会員データを活用「Ponta Ads」 / 株式会社ロイヤリティマーケティング【広告・マーケ事例インタビュー】
- クラウド・ソフトウェア・自社独自のノーコード開発ツール「CORE Framework」/株式会社STOVE
- 訪日インバウンドメディア「DiGJAPAN!(ディグジャパン)」/株式会社マップル【広告・マーケ事例インタビュー】
- 保有媒体は業界最大クラスの200媒体以上!ルートサンプリングなら株式会社KID GROUP HOLDINGS プロモーション事業部アドクロ【広告・マーケ事例インタビュー】
- 日本最大規模の歯科医師向けプラットフォーム「WHITE CROSS」/WHITE CROSS株式会社【広告・マーケ事例インタビュー】
- 人材不足をオンラインで解決「Web特命係」/株式会社米岡【広告・マーケ事例インタビュー】
- 日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」/株式会社ZOZO【広告・マーケ事例インタビュー】
- タレントをサブスクで起用できる「ACCEL JAPAN」/株式会社ブランジスタソリューション【広告・マーケ事例インタビュー】
- ECサイトの運営全般をサポート/株式会社ブランジスタソリューション【広告・マーケ事例インタビュー】
- ウェブマーケティング全般を支援/株式会社キヨスル【広告・マーケ事例インタビュー】


1952x1952.png.webp)