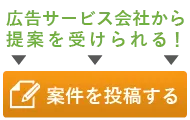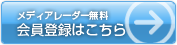国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト![]() (株)アイズ
(株)アイズ

更新日:2025年02月10日
企業がSNS活用するメリットは?ビジネスでの活用法や事例を解説!
 企業がSNS活用するメリットは?ビジネスでの活用法や事例を解説!
企業がSNS活用するメリットは?ビジネスでの活用法や事例を解説!SNS活用とは?
SNS活用とは、物の性能やサービスのメリットを十分に引き出し、使うことです。 では、SNSの性能やメリットとは何でしょうか? SNSとは、Social Networking Serviceの頭文字をとった略で、人々のつながりを促すサービスです。人々のつながりを促すため、匿名で情報を発信できたり、ハッシュタグで情報を収集できたり、「いいね」で共感を示せたりできる環境を整えています。こうしたつながりを促す環境で、個人は所属欲求や承認欲求を充たすため、企業は情報発信やブランディング、見込客を獲得するため、SNSを活用しています。
SNS活用の重要性
企業が、消費者とつながり、顧客との関係性を高めていく上で、SNS活用の重要性が増している根拠として以下の2つを紹介します。 SNSは、年々上昇する高い利用率から、消費者とつながる不可欠なチャネルとして機能するとともに、高いコンバージョン率が期待できるニーズ・ウォンツの明白な顕在顧客にリーチできる検索ツールとしても使われているのです。SNS利用率の上昇
ICT総研の2022年度調査によれば、2017年72.1%だったSNS利用率は5年で10%上昇し2022年82%に達するとのこと。総務省の令和2年調査でも、全世代でのLINE利用率は90%を超え、YouTubeも8割以上が利用し、SNSの主なデバイスとなっているスマートフォンの利用率は92.7%となっています。スマートフォンの携帯性と、テレビ利用率96.9%、PC利用率62.9%を考えると、消費者とつながるチャネル機能は、TVや新聞を超え、SNSが一番といえます。
実際、広告の世界では2019年にインターネット広告がTVCMを上回り、ソーシャル広告は全体の3割を超え、その中でSNS系の広告が最大規模となっているのです。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
参考:「2022年度SNS利用動向に関する調査」 ICT総研
参考:「2021年 日本の広告費」 株式会社電通
検索ツールとしての利便性の高さ
検索結果画面に掲載されるリスティング広告は、他の広告形式に比し高いコンバージョン率を誇ります。その原因は、検索を通じて明らかとなった特定のニーズ・ウォンツを持つ顕在顧客層に対してアプローチできるからです。 同じように顕在顧客層にリーチできる役割を果たしているのがSNSのハッシュタグ検索です。株式会社SHIBUYA109エンタテイメントの2019年調査によれば、20歳前後の女性の8割は、検索エンジンよりもInstagramでハッシュタグ検索しているとのこと。 投稿頻度の高さからくる「リアルタイム性」と信頼できる人たちの口コミの「信頼性」から、検索ツールとしてSNSの役割は今後もますます高まることが予想されるため、企業にとってSNS活用は重要です。
参考:『「ハッシュタグ(#)」に関する意識調査』株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
SNS活用に活かせる資料まとめ
SNS活用に関する資料を下記にまとめています。 企業向けのSNS活用の方法などが学べる資料もございますので、気になる方はぜひダウンロードしてお役立てください。 【SNS活用ノウハウ】フォロワー3万人の企業アカウント作り方_楽天ポイントギフト | 楽天グループ株式会社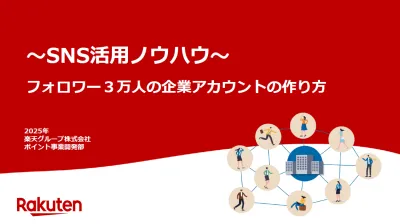
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【SNS活用×女性インフルエンサーマーケティング】Castbookサービス資料 | バリューコマース株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【SNS活用】完全成果報酬型インフルエンサー施策(主婦/ママ/Z世代向け事例有) | Performance Technologies株式会社
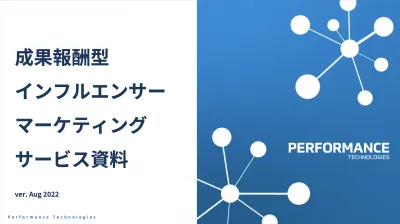
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【食品/旅行/アパレル】イベント集客に最適なSNS活用事例3選をご紹介 | CCCMKホールディングス株式会社
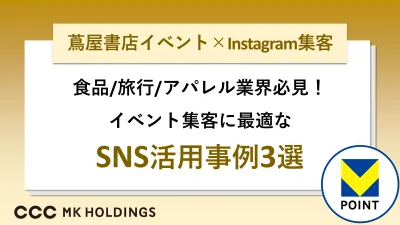
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【インフルエンサー美容師500名とエンゲージ】SNS活用の“売れる流通” | 株式会社セイファート

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)美容好き女性300人に聞いた好印象を持たれるSNS活用法 | 株式会社スリーツープロダクツ
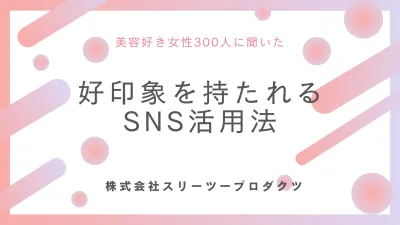
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)信用金庫×SNS活用|LINE・Instagram・Xによる顧客接点の強化事例 | 株式会社NYX|地域活性化!オリジナルクーポン冊子・サイト制作

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【Z世代向け】QJタイアップ|SNS活用で話題化・Youtube動画制作も可! | 株式会社太田出版

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【観光・レジャー特化】SNS運用代行&インフルエンサープロモーションで集客UP! | ONE HOPE株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)【タイ/インバウンド】外国人旅行情報メディアで認知向上/SEO上位・SNS活用! | 株式会社アジア・インタラクション・サポート

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
SNS活用のメリット
SNS活用のメリットは、SNS登場以前には実現できなかった優れたプロモーション手法を活用できたり、成果を即座に分析・改善することでより効果的な施策を展開できたりすることです。しかもこうした活動を無料または低予算で実現できるため、大企業に負けないプロモーションを、中小企業や個人事業主も展開できるようになっています。具体的には以下のようなメリットがあります。認知度の拡大による集客ができる
認知度拡大は、消費者の購買意思決定過程の始めに位置する重要なプロモーション活動です。認知度拡大には、ターゲットにあった媒体を使う必要があります。 この点、総務省の令和2年調査によれば、SNSの主な媒体となっているスマートフォンの利用率は全世代で9割(92.7%)を超えています。このうち、平日は45.2%、休日は43.1%がソーシャルメディアを利用し、メール(40.8%/34.9%)や動画サイト(27.7%/29.2%)を上回っています。20代に限れば7割弱(58.8%/57.7%)、10代では6割弱(58.8%/57.7%)に毎日リーチできるのです。このように、国民の約半数に毎日アプローチできるSNSの活用は、認知度拡大による集客に欠かせません。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
拡散力に特化している
拡散力は、ターゲットが使うSNS媒体の利用率の高さと同様、認知度拡大に有益な作用を及ぼすので、SNS活用のメリットです。 この点、X(旧Twitter)はリポスト機能で情報発信者が知らないユーザーまで情報が拡散します。基本的にフォロワーにしか情報や画像を届けられないInstagramも、ハッシュタグを使えばフォロワーを超え情報やコンテンツを拡散できます。ハッシュタグ文化が発達したTikTokでは、企業が作成したハッシュタグを起点にユーザーの自主的な投稿を促す「ハッシュタグチャレンジ広告」が人気です。
幅広い層にアプローチ可能
SNSは10代や20代の若い層だけが利用しているわけではありません。 総務省令和2年調査によれば、日本で最も利用されているSNSメディアLINEの利用率は、10代から40代までは95%前後、50代でも8割を超え、60代でも76.2%です。同じように全世代で高い利用率を誇るYouTubeも50代で8割、60代でも6割弱が利用しています。多くの企業が公式アカウントを開設しているFacebookは、実名制という障壁があるため、10代の利用率は2割未満ですが、社会人になると3割以上が利用し、30代に限れば約半数にリーチできる高いアプローチ力を持っています。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
ユーザーからの評価が把握できる
TV等アナログメディアに対する、デジタルメディアの大きなメリットは、メディア活動に対する反応を即時かつ正確に把握できる点です。PDCAサイクルでメディア活動を改善し、プロモーション効果を高められるのです。この点、SNSはビジネスアカウントを開設することで、様々なインサイト機能を使えるようになるだけでなく、ビジネスアカウントを開設しなくても、「フォロー」や「いいね」、リプライ等で、ユーザーからの評価を把握できるようになっています。
コンバージョン効果が見込める
商材の購買や会員登録、オウンドメディアへの流入等コンバージョンを高めるには、可能性のあるターゲットにアプローチできることや、行動を興すメリットを提供すること、競合品に対する優位性根拠を示すこと等が必要です。この点、SNSは、検索エンジンに代わる検索ツールとして利用されることでニーズ・ウォンツの明白な顕在顧客層にアプローチできるだけでなく、クーポンを配布して行動を興すメリットを提供でき、画像や動画で自社商材の魅力や世界観、強みを効果的にユーザーに伝えられます。
ファンの獲得・育成ができる
単なる潜在顧客層から見込客を選別し、購買客に育て、リピートや他者へ推奨するファンになってもらうためには、購買意思決定過程ごとに、最適なメディアを選択し、適切なアプローチ手法を展開することが必要です。 インターネット登場以前は、マスメディアに広告を出稿し、店舗でアプローチして購買を促しました。その後、製品改善活動で質を高めたり、アフターサービスを充実させたりすることでファンを獲得・育成してきました。しかし、SNSではこうした施策がSNSだけで完結できるようになっています。 SNSアカウントを通じた地道な情報発信やユーザーとの交流を通じて時間をかけて見込み客を獲得できますし、優れたターゲティング機能を持つSNS広告を使えば、即座に潜在顧客層から見込客を選別できます。ハッシュタグを通じた口コミの醸成やクーポン配布で購買を促し、購入後はSNSコミュニティ活動を開催したり、インフルエンサーを起用したりすることでファンに育成できるのです。
開設にコストがかからない
SNSで情報を発信したり、ユーザーとコミュニケーションしたりするには、そうした権利を取得するアカウント開設が必要です。企業がSNS運用する場合、個人アカウントとは別にビジネスアカウントを開設することが必要なSNSもありますが、これも無料で開設できます。例えば、Instagramでは企業のビジネスアカウントである「プロアカウント」を開設すると個人用アカウントでは使用できないインサイト機能やショッピング機能が使えたり、Instagram広告を出稿できたりしますが、開設自体は無料です。
参考:「Instagramでビジネスを始める」 Meta
ビジネスにおけるSNS活用の注意点
SNSは、そのメディアの特徴や提供サービスの多様性から様々なメリットを享受できます。しかし、その反面、その使い方を誤ると、期待通りの効果をあげられなかったり、不利益を被ったりすることさえあるのです。特にビジネス目的でSNSを活用する場合、経済的な損失やブランドを毀損するリスクがあるので、以下で具体的な注意点を紹介します。もっとも、ここで紹介する注意点をSNS運用で実際に活かすには、十分な経験やデータ、専門的な知識を要する場合があるので、その場合はSNS運用コンサルタントや運用代行業者に相談することが賢明です。
活用目的を定める
ビジネスのおけるSNS活用目的は、新規顧客獲得と既存顧客の関係管理に大きく分かれます。新規顧客獲得目的は、さらに認知獲得や興味関心醸成、比較検討情報収集、購買行為促進の4つに分かれ、顧客関係管理目的も、顧客関係キープと優良顧客育成の2つに分けられます。目的ごとに最適なSNSメディアと活用施策が異なるため、活用目的が不明確だと、効果的なビジネス活用ができません。例えば、SNSアカウントで商材情報を発信する場合、興味関心醸成目的では刺激的な言葉や画像で商材のメリットを伝える必要があるのに対し、顧客関係キープ目的では商材の使用例やメンテナス方法を丁寧に教える必要があるのです。
自社にあったSNS活用を
SNSは、メディアごとにユーザー属性やサービス内容に差異があるので、自社にあったSNSメディア活用が必要です。 BtoB取引をメインとする企業では、実名登録で社会人の利用率の高いFacebookで情報発信するのが、相手企業の信用を得る上で最適といえます。同じように日々の活動を伝える場合でも、BtoC取引をメインとする企業では、Facebook以外で情報発信する方が親しみやすい場合もあります。美容やアパレル関係なら、画像で世界観を伝えることが得意なInstagramを活用し、飲食店やクリーニング店等生活に密着した業種なら、チャット型の文章投稿メディアであるLINEでコミュニケーションとる方が良いでしょう。
ガイドライン・ルールを厳守した活用を
SNSは、その拡散性の高さ及び投稿の容易さから、いわゆる「炎上」トラブルやブランド毀損リスクの可能性が高いメディアです。そのため、事前にトラブル対応マニュアルやガイドラインを作成し、そのルールを厳守したSNSのビジネス活用が不可欠です。もっとも、こうしたSNSトラブルの対応には、十分な経験と知識が必要なので、SNS運用コンサルタント会社や運用代行業者にガイドラインやルールを作ってもらったり、運用を代行してもらったりする方が経済的な場合もあります。
業種別のSNS活用方法
業種ごとにターゲット属性や商材・サービス内容、ビジネスモデルに差異があるため、SNSの活用目的が異なります。活用目的が異なるので、SNS活用方法も業種別に差異が生まれるのです。 ここでは、一般的な業種特性を前提に、SNS活用方法を紹介します。 もっとも、同じ業種でも、実際のターゲットや商材、ビジネスモデルは異なるので、全ての業種例を参考に、よりマッチした活用方法を考えることをお勧めします。飲食店
飲食店のターゲット属性は、観光地の飲食店を除けば、狭い商圏内の社会人及び生活者です。 商材・サービス内容は、主に日常生活上必要となる最寄り品です。 ビジネスモデルは、オペレーション向上が成功のカギとなる労働集約型といえます。 従って、主なSNS活用目的は日々の集客で、その活用方法は、日常的なコミュニケーションとクーポン等販促物の配布です。例えば、LINEは、チャット型の文章投稿型メディアで、通信キャリアやデバイスを問わず通話できるため、電話に代わるコミュニケーションツールとなっています。クーポンも配布できるため、飲食店には最適なSNSといえます。
アパレル
アパレルのターゲット属性は、通信販売を除けば、自動車や公共交通機関で来店できる広い商圏に住む人です。 商材・サービス内容は、主に日常生活上必要のない贅沢品又は買回り品です。 従って、主なSNS活用目的は、日々の集客ではなく、ブランティングと一定期間ごとのキャンペーン促進といえます。そのため、活用方法は、企業や商材の世界観を伝えることや、キャンペーン時の情報発信、ハッシュタグの拡散です。例えば、Instagramは、動画や画像による投稿が多く、美容や食品に敏い30代までの若い女性に人気です。特定の趣味嗜好で形成されたコミュニティも強く、信頼できる口コミを求めたハッシュタグ検索も活発なので、アパレルには最適なSNSといえます。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
小売店
小売店のターゲット属性は、大型スーパーやショッピングセンターを除けば、狭い商圏内の生活者です。 商材・サービス内容は、日常生活上必要となる最寄り品から必要のない買回り品まで様々です。 従って、主なSNS活用目的は、最寄り品に関しては時間ごとの集客であり、買回り品に関しては週末の集客といえます。そのため、SNSの活用方法は、時間ごとのクーポン等販促物の配布や週末のお得情報の配信等が考えられます。例えば、X(旧Twitter)は、投稿が時系列順に表示される等、「今」を伝えるサービスに力を入れているので、お得情報に敏感なユーザーにアプローチできるSNSとして、小売店には最適です。
B to B企業
B to B企業のターゲット属性は、輸出に力を入れている企業を除けば、日本国内の企業です。 商材・サービス内容は、その購買決定に経済的合理的判断が必要な高額なコンテンツです。 従って、主なSNS活用目的は、恒常的な信頼関係の醸成と相手企業の合理的経済的判断材料となる情報の提供といえます。そのため、SNSの活用方法は、公式アカウントとして、ユーザーにとって有益な情報を定期的に発信することと、問い合わせに対する誠実な対応です。例えば、Facebookは、実名制の文章投稿型メディアとして、20代から50代までの社会人の利用率が高くなっています。そのため炎上等、投稿リスクが少なく、企業が公式アカウントとして活用するには最適なSNSです。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
SNSの始め方
SNSは、基本的に、アカウントを作成し、プロフィール設定すれば始められます。 メディアによっては、アカウント作成の前提として、専用アプリのインストールが必要であったり、企業活動の一環として利用する場合、ビジネスアカウントを別途作成する必要があったりするので注意が必要です。こうした準備やSNS運用をSNS運用代行会社に依頼する方が経済的な場合もあるのでこれもあわせて紹介します。参考:「新規登録をする」LINEみんなの使い方ガイド
参考:「X(旧Twitter)アカウントを登録する方法」ヘルプセンターアカウントを登録する方法」ヘルプセンター
個人の場合
個人がSNSを始める場合、2ステップで完了するのが一般です。SNSアカウントを登録し、プロフィールを設定するのです。もっとも、LINEなど一部のSNSメディアではアプリインストールが前提となります。 アカウントの登録とは、SNSメディアが提供している様々なサービスや機能を使用する権利を取得することです。登録には、認証手続きで必要となるメールアドレスと電話番号の入力が必要なので、手元にあるデバイスで受信できるアドレスと番号を入力しましょう。 プロフィールの設定とは、ユーザー名やプロフィール画像、パスワードを設定することです。主なSNSメディアではFacebook以外、実名登録は推奨されていないので、仮名入力で充分です。
企業の場合
企業がSNSを始める場合、個人とは異なる目的と活用方法を前提とするので、始め方が異なります。個人用アカウントとは別のアカウントが必要となったり、広告出稿準備のためプロフィール以外の設定が必要となったり、分析ツールの導入を要したりします。もっとも、具体的に何を作成して、どんな情報を設定する必要があるかは、メディアごとに異なるので、確認が必要です。使用するツールやデータ分析にも専門の知識や経験が必要となるので、アカウント作成を含めSNS運用代行会社に依頼することも視野に入れておきましょう。
企業用アカウントを使用
企業用アカウントを使用すると、個人用アカウントでは使用できないツールや機能、サービスが利用できるようになります。 但し、メディアごとに企業用アカウントの呼び名が異なるので注意が必要です。InstagramやX(旧Twitter)、TikTokでは「ビジネス」や「プロ」の名称が付されていますが、Facebookでは単なるFacebookページと称されるだけなので迷います。 また、メディアごとに開設が必要となるアカウント数も異なるので確認が必要です。例えば、Instagramではインサイト機能を活用したり、Instagram広告を出稿したりするには個人用アカウントの他に「プロアカウント」を開設する必要がありますが、TikTok広告を出稿するには広告専用アカウントを作成すれば足ります。
参考: TikTok for Business
SNS分析ツールの導入
企業がSNSを活用する場合、ブランディングやプロモーションを目的とするので、SNS運用には優れた費用対効果が求められます。そのためには分析ツールを導入してSNS運用を可視化することが必要です。 例えば、成果を高めるためには、市場動向や競合活動の分析、プロモーション効果を測定するツールが必要ですし、費用を抑えるためには、リスクモニタリングや自動入札ツールが必要となる場合もあります。もっとも、企業用アカウントを開設すると、様々なインサイトツールやショッピング機能をアカウント管理ツールで使えるようになるので、使用するSNSメディアごとに導入すべき分析ツールが異なります。そのため、ビジネス目的でSNSを始める前には十分な調査と検討が必要です。
SNS運用代行会社に依頼も視野に
SNS運用代行会社に依頼するメリットは、短期的には費用対効果を高め、長期的には将来の自社運用への近道となる点です。 InstagramやX(旧Twitter)など、既に企業参入の激しいSNSメディアで成果を上げるには高度な知識と習熟した経験を要します。未だ企業参入の乏しいSNSメディアで成果を上げるにも期間を要するのが一般です。この点、SNS運用代行会社に依頼すれば、直ぐに成果を上げることが可能ですし、その運用ノウハウや炎上対策が学べるので有益です。 予算を確保できるなら、SNS運用代行会社への依頼も検討しましょう。
各SNSの活用方法
各SNSの活用方法は、そのメディアの特性とユーザー属性により、異なります。また、活用者が個人か企業かにより主な目的が異なるので、活用方法を区別することが必要です。 個人が活用する場合、エンターテインメント目的と(所属及び承認)欲求充足目的に分かれ、企業が活用する場合、顧客獲得・育成目的とブランティング目的に分けられます。 こうした視点から、SNSメディア別の具体的活用方法を以下で紹介します。Facebookの活用方法
Facebookのメディア特性は、実名制です。アカウントに実名登録が推奨されるので、他のSNSメディアに比し利用障壁が高くなっています。一方実名制はリアルな社会でのコミュニケーションの延長を促し、投稿や口コミの信頼性を高め、炎上リスクを低減させます。 ユーザー属性は、総務省令和2年調査によると、利用率は3割程度で、男女比率は均等し、20代から40代のユーザーが平均を上回っている点が特徴です。このようなメディア特性とユーザー属性を有するので、企業が公式アカウントとして活用することが多く、投稿される内容も、つぶやきや会話ではなく、社会人としての日記や企業の活動報告がメインとなっています。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
Instagramの活用方法
Instagramのメディア特性は、写真や動画の投稿が多い画像共有型で、その世界観に共感するコミュニティが生まれやすい点です。 ユーザー属性は、総務省令和2年調査によると、利用率は4割程度で、男女比率は女性が高い5割弱で、10代から30代が平均を上回っている点が特徴です。 このようなメディア特性とユーザー属性を有するので、個人は信頼できるコミュニティの口コミを求めハッシュタグ検索し、企業は自社商材の魅力的な画像を投稿することでブランティングと顧客獲得を促しています。参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
LINEの活用方法
LINEのメディア特性は、チャット形式の文章投稿型で、デバイスや通信キャリアを問わず通話できる点です。 ユーザー属性は、総務省令和2年調査によると、利用率は9割を超え、男女比率は均等し、50代でも8割以上、60代でも7割を超える人に利用されている点が特徴です。 このようなメディア特性とユーザー属性を有するので、個人には、電話に代わる日常的なコミュニケーションツールとして活用されています。企業には、日本最大のユーザー数を抱えるメディアとして、消費者との交流を高め、クーポンを配信したり、ポイントカードを作成したりして購買行動を促すのに活用されています。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
TikTokの活用方法
TikTokのメディア特性は、短時間かつ作成の容易な動画コンテンツ投稿を可能にするサービスで、若者の承認欲求を充たす投稿を促している点です。 ユーザー属性は、総務省令和2年調査によると、利用率は2割弱で、男女比率は均等し、10代から20代が平均を上回り、特に10代に限れば6割弱に利用されている点が特徴です。このようなメディア特性とユーザー属性を有するので、個人には、スキマ時間を埋めるエンターテインメントメディアとして活用されるとともに、手軽な表現の場として利用されています。企業には、若者にアプローチでき、かつコラボレーションできる場として、プロモーションの共創に活用されています。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
YouTubeの活用方法
YouTubeのメディア特性は、オンデマンド型の長時間動画を無料で視聴できる点です。 ユーザー属性は、総務省令和2年調査によると、利用率は8割を超えており、男女比率は均等で、60代でも6割弱に利用されている点が特徴です このようなメディア特性とユーザー属性を有するので、個人には、テレビに代わるエンターテインメントメディアとして利用されると共に、収益を期待できる表現の場として活用されています。企業には、幅広いユーザーに、豊富な情報をインパクトのあるコンテンツで届けられるメディアとしてプロモーション活動とブランティング目的で活用されています。参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
SNS活用の事例
企業がSNSでプロモーションする際に参考になるSNS活用事例を紹介します。 他のメディアとは異なるSNS特有のサービスや機能を活用した事例や、SNSの特性を活かした利用例、SNSユーザーの属性を考慮した活用方法などです。こうした活用事例を参考にすることで、大企業に負けないプロモーションを展開できたり、費用対効果の優れた広告を出稿できたり、他のメディアではアプローチできない潜在顧客層にリーチできたり、多くのメリットを享受できるようになります。
ハッシュタグ(#)を活用する
ハッシュタグは、広告に活用する場合と検索キーワードとして活用する場合があります。 TikTokでは「ハッシュタグチャレンジ広告」が人気です。広告主が商材に関連するキーワードにハッシュタグを付け、そのハッシュタグに関連した投稿をユーザーに促す広告で、承認欲求の高いユーザーが多いTikTokの特性にマッチし、成果をあげています。 ハッシュタグ検索は、信頼できる口コミが期待できるInstagramや、「今」を伝えることに特化したX(旧Twitter)で盛んです。企業は商材や伝えたい情報にハッシュタグを付け、検索されるよう仕掛けをします。 例えば、日本マクドナルドは、「ハッシュタグチャレンジ広告」で5万件のユーザー投稿を獲得し、総再生数1億5000万回を実現しました。
参考:TikTok for Business
動画や画像で視覚的に訴求する
動画や画像は、短い時間でテキスト以上の情報を伝達できるコンテンツです。 視覚的に訴求できるのでインパクトが強く、認知獲得と興味関心の醸成が容易です。また、記憶に残りやすく、言葉の壁を越えたターゲットにも訴求できるので、広告の費用対効果を高めます。実際、株式会社電通の「日本の広告費」によれば、動画広告は、毎年20%以上の伸びを記録し、日本の広告市場の2割を超えるシェアまで成長しているとのこと。しかも、動画広告のデバイスの8割以上はスマートフォンで、SNSでの動画による訴求効果の高さを証明しています。 例えば、オンラインでサングラス販売を展開するWilliam Painterは、魅力的なデザインと質の良さをYouTube広告で訴求することで、前年比13倍の収益を達成しました。
参考:「2021年 日本の広告費」 株式会社電通
参考:YouTube広告
ユーザーに有益な情報発信を行う
企業がSNSを活用する場合、広告やインフルエンサー起用など、短期的なプロモーション成果を求める活動とともに、長期的に見込客獲得やブランティングを目指す活動も展開します。 長期的な活動で有効なのが、ユーザーに有益な情報を発信することです。交流を求めSNSを利用しているユーザーにとって、企業のプロモーション活動は嫌悪感を持って迎えられ、かえって炎上などマイナス効果を生むリスクがあるのに対し、有益な情報発信はユーザーに好意を持って迎えられるのです。こうしたSNSの特性を活かし、時には所属企業よりユーザー側に立って情報を発信することで、企業に利益をもたらしている例もあります。 例えば、SHARPの公式X(旧Twitter)は、ユーザー側に立った有益情報の発信で有名となり、「中の人」として親しまれています。
参考:SHARP シャープ株式会社 公式X(旧Twitter)
投稿内容に質問やアンケートを差し込む
SNSでの投稿内容に質問やアンケートを差し込む行為は、「ソーシャルリスニング」の一環として、企業の重要なSNS活用施策となっています。 ソーシャルリスニングとは、消費者の意見収集を主にSNSを通じて行うデータ活用手法で、従来のアンケート調査と異なり、SNSでの自由闊達な意見や行動履歴を集めるものです。そこで、自然な評判や口コミを把握することを目的として、アンケート調査形式をとらず、通常のSNS投稿に質問やアンケートを差し込むのです。 例えば、日清食品株式会社は、SNSに投稿された消費者の声をヒントに、カップ麺の「カップヌードル」2種類を組み合わせた新しいパッケージ商品を販売しています。
参考:『「カップヌードル スーパー合体」シリーズ』
投稿する時間とタイミングに注目
SNSは、24時間均等にアクセスされているわけではありません。総務省の調べによれば、平日には7時から8時、12時、20時から22時の3回、休日には20時から22時の1回、インターネット利用時間帯の山が認められました。通勤、昼休み、帰宅後など学生やサラリーマンの生活習慣に沿って、利用時間に差異が生まれています。 もっとも、X(旧Twitter)のような「今」を伝えることに特化したSNSメディアでは、こうしたアクセスの山が認められず、トレンド発生時に随時アクセス数が増える傾向があります。従って、ターゲットの生活習慣や活用するメディアの特性に応じて、投稿する時間とタイミングに注目することが、SNS活用では重要です。 例えば、花王株式会社は、コロナ禍で外出自粛が開始された2020年4月に、柔軟剤「花王フレアフレグランスシリーズ」の爽やかな写真をInstagramに投稿し話題を集めました。
参考:総務省 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
参考:「ハミングフレアフレグランス」花王
まとめ
SNSとは、人々のつながりを促すサービスです。 しかし、どのような人々のつながりを促すのか、どのように人々をつなげるのかの違いにより、メディアごとに提供するサービスが異なり、その結果、ユーザー属性も分かれています。 SNS活用にあたっては、このような提供サービスとユーザー属性の違いを考慮し、最適なSNSメディアと適切なサービスを選択しなければなりません。ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム


1952x1952.png)