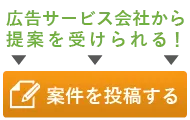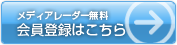国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト![]() (株)アイズ
(株)アイズ

認知拡大はSNSマーケティングの要!SNSで認知拡大を狙う理由とは?
 認知拡大はSNSマーケティングの要!SNSで認知拡大を狙う理由とは?
認知拡大はSNSマーケティングの要!SNSで認知拡大を狙う理由とは? SNSで認知拡大を狙う理由
SNSとは、英語のSocial Networking Serviceの頭文字をとった略で、社会的つながりを促すサービスです。 認知とは、商材の中身や企業の姿勢を知ってもらうことで、名前だけが知れ渡る知名度拡大と区別されます。 従って、SNSで認知拡大を狙う理由は、人々とのつながりを通じて商材の中身や企業の姿勢を知ってもらうことにあります。 TVや新聞等のアナログメディアと異なり、双方向の認知拡大であり、他のデジタルメディア以上に日常的で身近なコミュニケーションを通じて認知を拡げていく点が強みです。 SNSで認知拡大を狙う具体的な理由は以下の通りです。企業ブランディングが可能
ブランディングとは、商材や企業そのもののブランド価値やイメージを高めることです。 ブランドとは、英語で「brand」と記し、他者の家畜と区別するため押された焼き印に由来する言葉で、銘柄や商標を意味します。 他者との差別化を図り高価格設定や顧客とのチャネル獲得を容易にするものとして、ブランディングはマーケティングの上位概念と位置付けられています。 顧客と企業の2者間の関係を構築するマーケティングと異なり、第三者の評価や口コミが加わることでブランドは形成されるので、人々とのつながりを促すSNSは企業ブランディングに最適なメディアです。ユーザーからの生の声が届きやすい
TVや新聞等アナログメディアとSNSの一番の違いは双方向のメディアである点です。 しかも、他のデジタルメディア以上に日常的なコミュニケーションツールとなっています。 総務省の令和2年調査によれば、SNSの主なデバイスであるスマートフォンの利用率は全世代で9割を超え(92.7%)、このうち、平日は45.2%、休日は43.1%がソーシャルメディアを利用しているとのこと。国民の過半数に毎日アプローチできるSNSは認知拡大において一番重要な役割を果たしているのです。 こうした口コミや共感を通じてユーザーの生の声が潜在顧客層に届き、認知拡大に貢献しています。 参照:「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」総務省ユーザーとの信頼関係の構築
幕末からひろまった新聞や1953年に開始されたTVのように長年の実績からメディア自体が信頼性を有しているマスメディアと異なり、SNSはまだ普及して10年ほどです。 しかし、日常的かつ継続的なユーザーとのコミュニケーションが安心感や納得感を醸成し、SNSは信頼関係を構築しやすいメディアとなっています。 また、第三者たるSNSユーザーの口コミやハッシュタグが情報源として高い信頼性を有する点もSNSの強みです。 こうした信頼関係を構築しやすいSNSの特徴を生かして認知拡大を狙うことは賢明なプロモーション施策なのです。SNS内での販売促進もできる
販売促進とは、広義では、「自社や自社製品と顧客の間にどのような関係を構築していくか」の活動を示し、狭義では、消費者に直接アプローチして購入を促す仕掛けを意味します。具体的には割引やクーポン配布、特典を付与することでアプローチするのです。 SNSでは、日常的なコミュニケーションを通じて直接的に購入意欲を促せるサービスを簡単に展開できます。例えば、Instagramでは写真にタグを付けて購入サイトに誘導できますし、LINEではクーポンを簡単に配布できます。 こうしたSNSサービスを活用してユーザーとつながり、商材の中身や企業の姿勢を知ってもらうのです。拡散による「話題性」を狙える
総務省平成27年版情報通信白書によれば、自ら情報発信しているSNSユーザーは少数にとどまるが、他人の投稿を知人と共有することで情報を拡散させているユーザーは5割以上存在し、そのうち17%はほぼ毎日拡散させているとのこと。 具体的にはFacebookの「いいね」機能やX(旧Twitter)のリツイート機能を通じて情報が拡散されます。 こうして拡散された情報は、知人のつながりを通じて受け取ったり、第三者の口コミとして捉えられたりするので、受信者は広告以上に能動的に情報の中身に接し、「話題性」のある認知拡大効果を発生させるのです。 参照:平成27年版情報通信白書総務省【駅すぱあと Ads】電車移動の人へアプローチ!行動連動型アプリ内広告 | 株式会社ヴァル研究所

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【製造業向け】14万人超の会員に直接届く 独占メールマガジン広告でリード獲得 | Tebiki株式会社
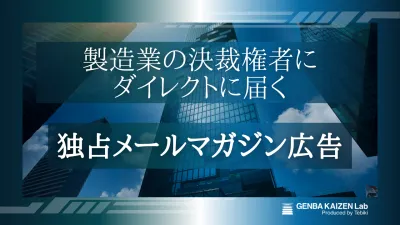
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【紹介動画で認知拡大】シニア向け動画・インフルエンサーマーケティングメニュー | 株式会社オースタンス
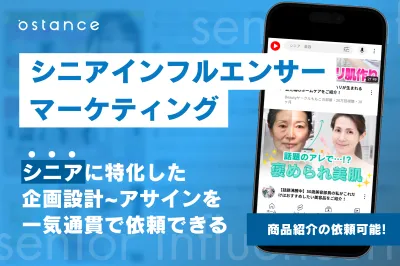
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【イベント集客/サンプリング】商業施設や公園、海での「野外シネマ」で認知拡大施策 | 株式会社WE TRUCK

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
約1.7億PV/月の日本最大級エンタメサイト・ 記事タイアップ広告 | 株式会社oricon ME

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
認知拡大の際に使用するSNSの種類
ユーザーとのつながりを通じて商材の中身や企業の姿勢を知ってもらうことを狙いとするSNSでの認知拡大では、メディアごとに主なユーザー層とサービスが異なるので、その特徴を生かしてプロモーションしなければなりません。
認知拡大の際に日本で一般的に使用されるSNSは以下の通りで、その特徴を示し、メディアごとの活用方法も紹介します。
Instagramとは、写真と動画がメインとして投稿される画像共有型SNSです。
Instagramのユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代の42.3%、女性に限れば全世代の5割が利用しています。10代20代では7割以上、30代でも5割以上がユーザーになっており、30代以下の女性とのつながりに強いSNSとなっています。
Instagramサービスの特徴は、飲食やコスメ、アパレル関係を中心に写真や画像が投稿され、若い女性の感性に訴える世界観が楽しめる点です。
従って、Instagramの特徴を生かした認知拡大方法は、画像や映像で表現する世界観を通じてユーザーと企業のつながりを促すことです。
参考:「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」総務省情報通信政策研究所
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)とは、280字以内のつぶやき形式の文章投稿型SNSです。
X(旧Twitter)のユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代の利用率が42.3%で、男女別の差異はありません。10代ユーザーは約7割に達し、20代では8割となっている点で若いユーザーとのつながりに強いメディアとなっています。
X(旧Twitter)サービスの特徴は、短文のテキストがタイムラインに流れることで「今」を伝えるトレンド性と、リポスト機能で全く知らないユーザーまで情報が伝わる拡散性です。
従って、X(旧Twitter)アカウントを登録する方法」ヘルプセンターの特徴を生かした認知拡大方法は、「今」を伝えることで、通常ではアプローチできない潜在顧客層と企業のつながりを促すことです。
参照:総務省令和2年調査
LINE
LINEとは、日本最大のユーザー数を誇るチャット形式の文章投稿型SNSです。
LINEのユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代の9割に利用され日本で一番普及しているSNSメディアです。50代でも85.4%、60代でも76.2%がユーザーであり、電話に代わるコミュニケーションツールとなっています。
LINEサービスの特徴は、会話形式で家族や友人とコミュニケーションするサービスを無料で提供していることです。さらに自動返信機能やメッセージの一斉配信機能で、電話以上に簡便なコミュニケーションを実現しています。
従って、LINEの特徴を生かした認知拡大方法は、日常的な会話を通じてユーザーと企業のつながりを促すことです。
参照:総務省令和2年調査
YouTube
YouTubeとは、長時間動画の投稿・共有型SNSです。
YouTubeのユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代の85.2%が利用し、男女別の偏りはありません。50代でも8割以上が利用しTVに代わる映像メディアとなっています。
YouTubeサービスの特徴は、TVと同等の長時間動画コンテンツをいつでもどこでも無料で視聴できることです。
従って、YouTubeの特徴を生かした認知拡大方法は、映像を通じて商材体験や企業のブランドストーリーを伝え、幅広い年代のユーザーと企業のつながりを促すことです。
参照:総務省令和2年調査
TikTok
TikTokとは、縦型ショート動画の投稿・共有型SNSです。
TikTokのユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代では17.3%と、まだ普及途上のメディアです。しかし、10代では約6割がユーザーであり、若年層のつながりを促すSNSとなっています。
TikTokサービスの特徴は、映像制作の初心者でも簡単にBGM付きのショート動画を投稿できることです。こうしたサービスが若者の承認欲求を喚起し新しいクリエイターを継続的に生み出しています。
従って、TikTokの特徴を生かした認知拡大方法は、ユーザーの承認欲求を充たすプロモーション施策を通じてユーザーと企業のつながりを促すことです。
参照:総務省令和2年調査
Facebookとは、実名制の日記型文章投稿型SNSです。
Facebookのユーザー層は、総務省令和2年調査によれば、全世代で31.9%が利用し男女別に差異がありません。20代から40代までの利用率が平均を上回っている点で社会人のつながりに使われているSNSといえます。
Facebookサービスの特徴は、実名制を通じてリアル社会でのコミュニケ―ションをデジタル空間で実現できる点です。
従って、Facebookの特徴を生かした認知拡大方法は、リアル社会での立場でのつながりをデジタル空間でも実現することです。
参照:総務省令和2年調査
認知拡大におすすめなSNS施策
SNSで認知拡大を狙う理由は、人々のつながりを通じて商材や企業の中身を知ってもらうことです。このつながりをもたらすのが以下で紹介するSNS施策です。
見込客獲得とブランディングのため、SNSはホームページのように活用され、潜在顧客層及び既存顧客との親密なつながりを実現するため、SNSはコミュニケーションツールとして利用されます。また、短期的な集客のため、SNS広告を出稿し、SNSのインフルエンサーをプロモーションに起用します。
SNSキャンペーン
キャンペーンとは、特定の目的をもって、大衆に対して組織的な働きかけすることです。
企業のプロモーションとして行われるSNSキャンペーンは、ユーザー参加型の行動喚起施策を意味します。
SNSでもクーポンや割引等プレゼント付与型のキャンペーンも行われますが、メインはユーザー参加型です。
新製品の認知拡大や季節ごとのプロモーション目的で、SNSユーザーの投稿を呼びかけるキャンペーンが人気で、ハッシュタグ文化が育っているInstagramとTikTokでは、企業制作のハッシュタグを付けて商品やサービスを利用してもらったり、ハッシュタグにあうコンテンツを投稿してもらったりしています。
こうしたユーザーの主体的参加を通じてつながりをもつことで商材の中身や企業姿勢を知ってもらうのです。
SNS広告
広告とは、英語で「advertising」と記し、広く知らしめることを意味します。
同じように大衆への認知を目的とする広報と異なり、知らしめる施策を展開するのにコストを要することが広告の特徴です。そのため、SNS広告は、ペイドメディアと呼ばれ、短期的な集客を目的とします。
SNS広告の特徴は、詳細なターゲティングと迅速かつ効果的なPDCAサイクルが可能なことです。SNSの行動履歴や利用履歴を通じて取得したデータで他のWeb広告以上に希望する顧客属性を有するユーザーに広告を通じてつながり、アナログ広告では不可能な迅速かつ正確な広告成果データを取得して広告施策を改善し効果的効率的な認知拡大を実現できるのです。
インフルエンサーの起用
インフルエンサーとは、影響や感化を意味する「Influence」を語源とする言葉で、広義では、メディアを通じてユーザーに影響を及ぼす人ないし企業を示し、狭義ではSNSを通じてユーザー及びそのコミュニティに影響を及ぼす人ないし企業を意味します。
YouTubeのインフルエンサーは「YouTuber」、Instagramのインフルエンサーは「Instagramer」、TikTokのインフルエンサーは「TikToker」という風に、SNSのインフルエンサーも細分化され、その属性や影響力の質もメディアごとに異なる点が特徴です。
認知拡大にインフルエンサーを起用することは、その影響を受けるユーザーやコミュニティにつながることを意味し、その影響力を利用して効率的かつ効果的に商材の中身や企業姿勢を知ってもらうことに価値があります。
但し、インフルエンサーが影響を及ぼせるユーザー及びコミュニティは特定の属性を有し、認知拡大を目指す商材や企業とマッチせず、期待通りの成果を上げられないこともあります。そのため、インフルエンサーの起用は慎重を要し、インフルエンサー事務所やポータルサイトの活用を検討することも賢明です。
認知拡大するためのポイント
SNSで認知拡大を狙う理由は、人々のつながりを通じて商材の中身や企業姿勢を知ってもらうことでした。ここではアナログメディアや他のデジタルメディアには無いSNSサービスの特徴を生かし、人々とのつながりを通じて認知拡大するポイントを紹介します。
いずれもSNSの強みとなっているサービスなので、このポイントを活かすことにSNSで認知拡大する価値があります。
効果的なハッシュタグの選考
ハッシュタグとは、英語で「hash tag」と記し、「hash」はコマ切れを、「tag」はデジタル上の指示を意味します。
SHIBUYA109エンタテイメントの調査によれば、20歳前後の若い女性の8割がGoogle検索よりInstagramでハッシュタグ検索して情報収集しているとのこと。
従って、企業は効果的なハッシュタグを選考することで、自社オウンドメディアに誘導して商材や企業の中身を知ってもらえます。
Instagramと同じようにハッシュタグ文化が育っているTikTokでは、企業が作成したハッシュタグに合ったコンテンツをユーザーに投稿してもらう「ハッシュタグチャレンジ広告」が人気で、成果を上げています。
参照:『「ハッシュタグ(#)」に関する意識調査』株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
顧客育成に繋げるためのメッセージ
プロモーションにおける顧客育成とは、広義では、顧客獲得・顧客維持・顧客関係強化の全過程を示し、狭義では顧客関係強化だけを示します。
ここでは認知拡大するためのポイントとして広義の顧客育成を意味します。
こうした顧客育成は購買意思決定過程を通過させることを主な目的とするので、伝えるべきメッセージは、認知(Attention)段階、興味関心醸成(Interest)段階、比較検討情報収集(Search)段階、購買(Action)段階、共有(Share)段階で区別されている点が特徴です(AISAS理論)。
このうち認知段階で載せるべきメッセージは、商材や企業の名前や特徴がターゲットに分かり易くかつ覚えやすくなっていることが必要で、興味関心醸成段階では欲求を喚起するメッセージが求められます。
親近感の醸成
親近感を醸成するとは、SNSユーザーを「他者へ推奨するつもり」の心理状態にすることです。
マーケティングの権威、フィリップ・コトラーによれば、「企業または商品サービスへのSNSコミュニティの愛着推奨」は、SNSコミュニティへ企業が類似接触や互酬接触、単純接触することで醸成されます。
類似接触とは、人は、同じような趣味や考え方をもつ人を好む傾向にあるとする法則を利用した接触方法で、SNSコミュニティとワークショップを開いたり、検索連動型広告を出稿したりすること等です。
互報接触とは、小さなプレゼントを贈り合うことでお互いに好意を持つことになるという法則を利用した接触方法で、Instagramで「いいね」したり、LINEでスタンプをプレゼントしたりすることです。
参照:マーケティング4.0とは?
投稿頻度を高める
SNSで投稿頻度を高めることは、フィリップ・コトラーが「企業または商品サービスへのSNSコミュニティの愛着推奨」を得るために必要な施策として紹介している「単純接触」です。単純接触とは、単純にコミュニケーション頻度を上げることで愛着を獲得しやすくなる法則を利用した施策で、X(旧Twitter)で常にトレンド性のある話題をつぶやいたり、LINEで日常的にコミュケーションしたりすること等が該当します。
もっとも、投稿頻度を高めることは、SNS運用負担を増やし、炎上リスクを高めるので、SNS運用代行企業を活用することも経済的かつ懸命な選択肢です。
SNSにおける認知拡大のアイデア
ここで取り上げる認知拡大のアイデアは、アナログメディアや他のデジタルメディアでも活用される一般的なものです。しかし、SNSでのプロモーション競争が激しくなっている今日、こうした定番のアイデアをSNSで活かすことは最低限必要です。
以下では、SNSの特徴を生かし、人々のつながりを通じて商材や企業の中身を知ってもらう具体的な認知拡大のアイデアを紹介します。
顧客の悩みに寄り添った商品・サービスの紹介
商品の存在や企業の名前を知ったSNSユーザーに、商材の中身を知ってもらい、企業ブランディングするには、顧客の悩みに寄り添った商品・サービスを紹介しなければなりません。
こうした紹介で興味関心を醸成するには、SNSメディアごとの特徴に応じた最適なコンテンツを提供することが必要です。
文章投稿がメインとなるFacebookやLINE、X(旧Twitter)ではターゲットの欲求を喚起するメッセージやつぶやきでの紹介が必要であり、動画投稿がメインとなるTikTokやYouTubeでは悩み解決ストーリーや体験談が求められます。若い女性ユーザーの多いInstagramでは悩み解決後の世界観を連想できる画像を投稿することで、ユーザーとのつながりを強め商材の中身を知ってもらいやすくなります。
競合他社を分析してみる
競合他社を分析してみることは、SNSでの認知拡大などの具体的なプロモーション施策を展開する前に行わなければならないマーケットの基本です。
競合他社分析では、売上や利益率、シェア等の定量データの他、商品力やマーケティング力、ブランディング力等の定性データも収集分析しなければなりません。
SNSの認知拡大では、どのSNSメディアを活用しどのようなコミュニケーションしているのか、その運用体制や費用対効果などを調査分析することで、競合他社の弱みを突き、自社の強みを活かせるSNSユーザーとのつながり手法を見つけられます。
自社だけが解決できる悩みに焦点を当てる
SNS以外のメディアを使った場合でも自社だけが解決できる悩みに焦点をあてたプロモーションはマーケティング成功のカギとなっています。
しかし、他のメディア以上に詳細なターゲティングと密接なコミュニケーションが可能なSNSでは、こうした悩みに焦点をあてることでより費用対効果の優れたプロモーションを展開できます。
年齢や性別、家族構成、地域、趣味だけでなく、使用デバイスや視聴時間等で、解決できる悩みをもったユーザーに的確にアプローチし、テキストや画像・動画等最適なコンテンツで自社だけが解決できることを紹介することで、商材の中身や企業姿勢を知ってもらえるのです。
コメントへの反応でコミュニケーションを取る
人々のつながりを通じて認知拡大するSNSでは、投稿のコメント欄やDM、アンケート機能を通じて寄せられるユーザーの反応へのコミュニケーションが重要です。
特に短文のリアルタイム投稿が特徴であるX(旧Twitter)では、SHARP等企業のSNS担当者の柔軟な対応が「中の人」として人気を博し、自社製品の認知拡大や企業ブランディングに貢献しています。
もっとも、企業の対応次第で炎上するリスクもあるので、コメントへの対応は知識と経験を有し、SNS運用代行企業に依頼する方が賢明な場合もあります。
SNSでの認知拡大においての注意点
SNSで認知拡大を狙う理由は、人々のつながりを通じて商材の中身や企業の姿勢を知ってもらうことです。しかし、より効果的かつ効率的に認知拡大するには競合他社と差別化されたアプローチしなければならず、つながりを深めるに適するSNS特有の運用体制を構築しなければなりません。
認知拡大においての具体的な注意点は以下の通りです。
競合他社と異なったアプローチを行う
SNSでの主なアプローチ施策は、キャンペーンや広告、インフルエンサーの起用でした。
こうした施策も競合他社と同じようなアプローチを展開していては、SNSの詳細なターゲティング機能や親密なコミュニケーション機能を活かしたことにならず、認知拡大にSNSを利用する意味が薄れてしまいます。
また、SNSでのアプローチ手法は、大きく3つに分かれており、オウンドメディアとしてSNSを活用する場合、その目的はブランディングや認知拡大で、Facebookをホームページの代用とするのがその代表例です。アーンドメディアとしてSNSを活用する場合、その目的はユーザーとのコミュニケーションの向上で、トレンドが発生した場合にX(旧Twitter)で適時つぶやいたり、LINEで日常的に連絡をとったりします。ペイドメディアとしてSNSを活用する場合、その目的な短期的な集客で、SNS広告を出稿したり、インフルエンサーを起用したりします。こうした多様な手法の中から競合他社と異なったアプローチを選択することで効果的な認知拡大を実現できるのです。
運用体制を整える
SNSで運用体制を整える際の注意点は、ユーザーとの継続的なコミュニケーションする上でのメリットとデメリットを充分に調査分析して、負担とリスクに対して適切に経営資源を配分することです。
SNSでの運用体制は自社運用する場合と運用代行企業に委任する場合に分かれます。
それぞれの運用体制で得られるメリットとデメリットが大きく異なるので、自社の経営資源と用意できる予算、中長期的なSNS運用目的などを総合的に考慮して運用体制を整えなければなりません。
自社だけ運用体制を整える場合、知識や経験が蓄積できるメリットがありますが、運用に失敗すると炎上したり、ブランドイメージが毀損したりするリスクが発生します。
SNS運用代行企業に委任する場合、短期的には費用対効果に優れ、コアコンピタンスに経営資源を集中できるメリットがありますが、知識や経験が蓄積できず、いつまでも自主運用できないリスクが発生するので注意が必要です。
SNSで認知拡大に成功した事例
SNSでの人々のつながりを通じて商材の中身や企業姿勢を知ってもらうことに成功した事例を取りあげます。効率的かつ効果的にユーザーとのつながりを実現するツールや企業のサポートを受けて認知拡大に成功した事例や、つながりを促すコンテンツを提供するに最適なSNSメディアを活用して認知拡大に成功した事例などです。どのような課題解決のためSNSやサポートツールを選択したか、整理して紹介します。
株式会社 uzumaki creative【Instagram①】
公式ファンコミュニティを特定ターゲット世代にバズらせるツールを導入して成果を上げた事例です。
ツールを開発したのはZ世代向けSNSマーケティング事業を展開している株式会社uzumaki creativeで、ツールを導入したのは定食や牛めしを提供しているファストフードチェーンの株式会社松屋フーズの公式ファンコミュニティ「松屋研究会」です。
松屋研究会の課題は、従来顧客層ではなかったZ世代(10代前半から本格的な労働所得を獲得し始める26歳前後まで)に認知拡大することでした。
そこで、株式会社uzumaki creativeが提供しているARフィルターを活用してSNSで認知拡大することにしたのです。
このARフィルターは、現実世界を映す写真や動画にデジタル加工するもので、Instagramのリールやストリーズの投稿に活用できます。
こうしたツールを導入し、承認欲求を刺激して若者につながることで認知拡大に成果を上げました。
なお、「松屋研究会」は2022年6月30日をもって終了しています。
参照:Z世代向けSNSマーケティング事業を展開するuzumaki creativeが株式会社松屋フーズ「松屋研究会」のInstagram ARフィルターをリリース
株式会社有隣堂【YouTube】
店員の熱意と独自キャラクターとの掛け合いをYouTubeで発信することで20万人越えの登録者とのつながり実現している事例です。
株式会社有隣堂は、神奈川県を中心に東京や千葉でも本屋を展開する創業100年を超える書店チェーンです。
課題は、差別化と収益化の難しい街の本屋というビジネスモデルの中で、独自の地位を獲得することでした。
そこで、全世代に満遍なくアプローチでき、創業100年の企業ストーリーと社員及び取扱商品の個性を映像で伝えられるYouTubeを活用することにしたのです。
当初は本紹介など個性のない動画コンテンツだけで反響がなかったため、独自キャラクターを導入し、取扱商品より社員の熱意を伝えることに方向転換することで、有隣堂自体のファンを増やし登録者増加に成功しています。
参照:有隣堂
:有隣堂しか知らない世界
:毒舌キャラが「地方の弱小書店」と呼び人気…有隣堂ユーチューブ、登録者22万人突破
全日本空輸株式会社【TikTok】
従来の顧客層とは異なる世代にSNSを通じてつながることで認知拡大に成功している事例です。
全日本空輸株式会社は、ANAホールディングスの航空運送を担当する企業で、ANA又は全日空と呼ばれています。
課題は、コロナ過で停滞した空の旅を回復させるため、従来のメイン顧客層でない若者へ認知拡大することでした。
そこで、多様な情報を短時間で提供できるショート動画を投稿でき、若者がメインユーザーとなっているTikTokを活用することになったのです。
若者に馴染みが薄い航空産業の仕事内容を伝え、距離を近づけるためにANAグループ社員が制服で踊るショート動画「何している人」シリーズを毎日投稿し、現在までコンテンツは500本を超えています。260万再生超える動画も出現し若者とのつながりに成功しています。
参照:ANA
TECOBI【Facebook】
SNS広告と独自の顧客関係管理(CRM)システムで質の高い見込客獲得と獲得単価減少を両立させている事例です。
TECOBIは、主に自動車業界のコミュニケーション及び広告ソリューションを提供するデジタルマーケティング企業です。
課題は、クライアント先の売上を伸ばすため、質の高い見込客を見つけることでした。
そこで、独自のCRMとコンバージョンAPI(PCやスマホへの指示言語)を統合したデータでFacebook広告キャンペーンを展開することにしたのです。
ABテストを通じてキャンペーンを改善していくことで、質の高いリードに最適化された広告を出稿できるようになっています。
質の高い見込客にSNS広告を通じてつながれることで、クライアントのコンバージョン率が68%上昇し、リード獲得単価が8%減少しました。
参照: 「TECOBI Facebookリード獲得広告とコンバージョンAPIで質の高い自動車購買層へリーチ」
まとめ
SNSで認知拡大を狙う理由は、人々のつながりを通じて商材の中身や企業姿勢を知ってもらうことにありました。
ターゲットにアプローチできるSNSメディアを活用し、そのメディアの特徴を生かしたメッセージや画像を通じてユーザーとのつながりを促すことが必要です。
詳細なターゲティングと親密なコミュニケーションで、他のメディアには無い認知拡大が図れます。
通常の顧客層と異なる若者にアプローチするためTikTokチャネルを開設したANAは、グループ社員の個性あふれるダンス動画を通じてANAの仕事内容と提供しているサービスを知ってもらうことに成功しました。
ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム