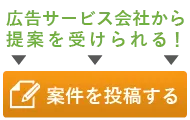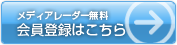国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト![]() (株)アイズ
(株)アイズ

更新日:2023年05月19日
ターゲティングとは?方法や成功事例を徹底解説!
_1920x1280.jpg.webp) ターゲティングとは?方法や成功事例を徹底解説!
ターゲティングとは?方法や成功事例を徹底解説!ターゲティングとは
ターゲティングの意味
英語では「Targeting」と書き、マーケティング用語として、セグメンテーションされた市場や顧客層を標的設定することを意味。広告用語として、インターネット利用者の検索履歴やサイトのコンテンツ内容などを分析して、その利用者の興味や関心事に応じた広告を配信する、いわゆるターゲティング広告を意味します。マーケティング用語としてターゲティングとは
マーケティング用語としてターゲティングは、消費者を分析するフレームワーク「STP」のTに位置します。マーケティングの権威、フィリップ・コトラーによれば、全てのマーケティング戦略の基本はSTPにあると言われるほど重要な手法の1部です。すなわち、セグメンテーション(Segmentation)、Targeting、ポジショニング‘(Positioning)で構成され、「どの」セグメントを「いくつ」標的とするか決めることがターゲティングといえます。「どの」「いくつ」でさらにターゲティングは3から5種類に分類される点が特徴です。
▼画像をクリックで無料会員登録!
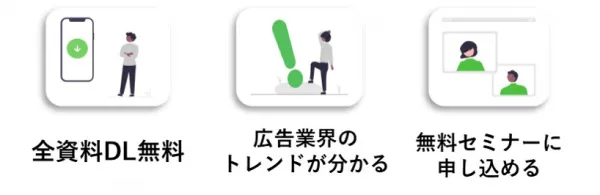
コトラー型ターゲティングの種類
コトラーは、ターゲティングを以下の3種類に分けています。・「無差別型」:標的セグメントを決めずに、共通の製品・サービスを提供
・「差別型」:複数のセグメントを決め、それぞれのセグメントに異なる製品・サービスを提供
・「集中型」:特定のセグメントを決め、そのセグメントに製品・サービスを集中的に提供
エーベル型ターゲティングの種類
コトラーよりも詳細なターゲティング5種類論です。・「フルカバレッジ戦略」
「フルカバレッジ無差別型」:個々のセグメントすべてに対し、共通の製品・サービスを展開
「フルカバレッジ差別型」:個々のセグメントに対して、個別の製品を開発しマーケティングを展開
フルガバレッジ戦略が採用できる企業はGAFAやヤフー、Toyotaなどごく少数の世界的企業に限られます。多くの企業は資金面や人材面で限界があるので、相対的に有望ではないセグメントはそれ以上検討することを避け、より有望なセグメントをターゲットとする戦略に集中していく、以下のような専門化戦略を採用するのが一般です。
・「市場専門化戦略」:特定セグメントにこだわり、新製品を投入していく戦略
・「製品専門化戦略」:特定製品・サービスにこだわり、新市場へ投入していく戦略
・「選択的専門化戦略」:特定セグメント複数に、多様な製品を投入していく戦略
M&Aなどで多様な企業や製品を取り込んだコングロマリット的な企業が選ぶ戦略です。
・「集中型ターゲティング戦略」:単一セグメントへ資金も人材も集中する戦略
広告用語としてのターゲティングとは
ターゲティング広告の種類
広告用語としてのターゲティングは、ターゲティング広告を意味し、以下の5種類に分けられるのが一般です。・「オーディエンスターゲティング」:クッキー(Cookie)を通じて取得した検索履歴やサイト訪問履歴、商品販売履歴、サービス利用履歴などの資料を基に抽出したユーザー属性や行動パターンに基づいて適切な「人」に配信。
・「コンテンツターゲティング」:広告する自社商材と同種の「コンテンツ」を掲載するサイトに広告を配信。
・「デバイスターゲティング」:広告配信先のデバイス(PC、スマホ、タブレット)を限定して配信
・「ジオ(位置情報)ターゲティング」:インターネットで紐づけされている「位置情報」を基礎に広告を配信
・「リターゲティング」:ユーザーの「訪問履歴」などを基礎に広告を配信
【関連記事】ターゲティング広告とは?仕組みと種類を一括比較
ターゲティングができる広告媒体やマーケティング資料の紹介
下記にて、訴求先をターゲティングできる広告媒体やマーケティング手法の資料をご紹介しますので、ぜひお気軽にダウンロードしてみてくださいね。【駅すぱあと Ads】電車移動の人へアプローチ!行動連動型アプリ内広告 | 株式会社ヴァル研究所

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【ペット飼育者約18万世帯】富裕層の飼い主にアプローチ | オイシックス・ラ・大地株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【中学生/高校生/大学生のZ世代へ効果的に広告掲載!】10月-12月媒体資料 | スタディプラス株式会社
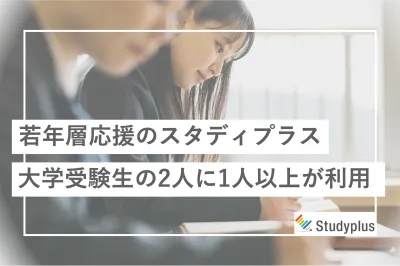
資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【医師・看護師】全国で使われる医療介護SNS 会員34万人へセグメントメール配信 | エンブレース株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【食べログ広告】約9,400万人のグルメ関心層にタイアップやサンプリングでPR | 株式会社カカクコム

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
VTuberファンをターゲティングできる購買データあります。 | 株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【日テレTVer】視聴データ分析でターゲティング!『インストリーム動画広告』 | 日本テレビ放送網株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【圧倒的訴求力のOOH】AIで効果測定+行動計測!車両サイネージ(アドトラック) | 株式会社WE TRUCK

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
GEO FiELD プレママ・産後ママターゲティング広告 | 株式会社中日アド企画

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
【全国映画館対応】Z世代の来場急増!“最も注視される”映画館メディア | 株式会社サンライズ社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)
ターゲティングの重要性
消費者のニーズウォンツに応えるためのターゲティング
1970年代、生産性が向上し、需要と供給のバランスがとれはじめたため、消費者に届ければ売れるという単純な産業構造でなくなり、競合企業が増えたため価格競争が生じ、マーケティングは製造側主導から、消費者志向に変化しました。このため、マーケティングリサーチの重点は市場のボリュームから質の判断の基礎となるデモグラフィックに移り、消費者を分析するフレームワークとして開発されたのがSTP分析です。企業は市場やターゲットを絞ったうえで、製品やサービスを生みださざるを得なくなり、ニーズに優先順位をつけることで、より適切な製品を提供することが可能になりました。1990年代、インターネットが普及、欲しいものがすぐに手に入り、比較検討情報も閲覧、ダウンロードでき、自らコラム等で情報も発信できる環境の中、ニーズウォンツはますます先鋭化。
2010年代、スマホの普及とともに、SNSでのコミュニケーションは常態化。消費者の嗜好がさらに細分化。
このように、消費者のニーズウォンツに応えるターゲティングの重要性が増加し続けています。
企業活動効率化のためのターゲティング
競合企業が増えたため価格競争に入る一方、製造される「モノ」自体がコモディティ化し競争力が失われ、第2次産業の景気が後退。各企業は生き残りのため、費用対効果の視点が重視され、ビジネス活動全体の効率化が現在のテーマです。より詳細なターゲティングでマーケティング活動自体の効率化、ターゲティングした対象にのみ広告を打つことが必要になっています。より詳細なターゲティングを可能にしているテクノロジーの発達
1990年代以降、インターネットが普及するとともに、web広告が発達。2010年代に入ると、日常のコミュニケーションツールとなったSNSでの広告も登場。
目的に応じてきめ細かく集客運用できるweb広告は、オフライン広告よりコストパフォーマンスに優れ、年齢、性別、地域など細かくビジネス活用できるSNSは、コミュニケーションツールとして接触する時間が増え続け、広告メディアとしての重要性が増しています。
さらに、AIとクラウドが業種業態を超えたデータ獲得と分析を可能にし、5GとIOTの普及は、その範囲を広げ、スピードを上げていくでしょう。
このため、重要性を増しているターゲティングをより詳細に展開することを可能にしています。
ターゲティングのフレームワーク
フレームワークとは
フレームワークとはframeworkと書き、枠組み、骨組み、構造、組織などを意味する他、問題に取り組むための方法を体系化した枠組みのことを意味します。マーケティング用語としてターゲティングのフレームワーク
マーケティング用語としてターゲティングのフレームワークは、ターゲティングに値するセグメントを選ぶためのフレームワークと効率的なターゲティングのためのフレームワークに大別されます。そして後者は「6R」と「CRM」を使うのが一般です。ターゲティングに値するセグメントを選ぶためのフレームワーク
・測定可能性:セグメンテーションの規模、購買力、特性が測定できること・利益確保可能性:セグメントが、製品やサービスを提供するのに十分な規模と収益性を有していること
・接近可能性:セグメントに効果的に到達し、製品やサービスを提供できること
・実行可能性:セグメントに製品やサービスを提供するのに、効果的なプログラムを設計できること
・差別化可能性:セグメントが概念的に区別でき、マーケティングミックス要素が異なれば、それに対する反応も異なること
効率的なターゲティングのためのフレームワーク
「6R」
・Realistic Scale:市場規模は適切か・Rate of Growth:成長は見込めるか
・Rank/Ripple Effect:顧客の優先順位と波及効果は高いか
・Reach:顧客に到達できるか
・Rival:競合他社は激しくないか
・Response:マーケティングミックスへの反応は測定可能か
「CRM」
顧客関係管理ツール「CRM」は顧客情報に加え、営業支援ツールとして営業情報も分析できるので効率的なターゲティングのためのアプローチに使えます。「リピーターになりやすい企業が抱えている課題は何か」「売上と企業規模の関連性は」などが一目で分かりターゲティング効率化に使うメリットが大きいのです。広告用語としてのターゲティングのフレームワークとは
効率的なターゲティング広告のためのフレームワークとしてSTPのP、ポジショニングの考え方が役に立ちます。ポジショニングとは、企業の提供物やイメージを、標的市場で認識されるために特有の位置を占めるよう設計する行為です。その位置づけのため、ターゲティング広告が重要になります。コトラーは、経営資源を量と質で分けて、4つのポジショニング戦略を提案。マーケットリーダーが取るべきポジショニング戦略
・基本は、市場の2番手3番手がとった戦略と同一の戦略をとって、市場シェアを守り抜くことを目指します。同サイズ同タイプの車を後発に出すトヨタがよく取る戦略です。2番手以降にあるチャレンジャー企業が取るべきポジショニング戦略
・リーダー企業の弱いところを崩すか、規模の小さい会社を潰す戦略をとります。経営資源の量も質もリーダーやチャレンジャーに劣るフォロワー企業が取るべきポジショニング戦略
・リーダー企業の戦略を真似しながら追いかける戦略。経営資源は少ないものの、他にはない技術を持っている又は価値を提供できる企業が取るべきポジショニング戦略
・リーダー企業がカバーできない小規模市場でリーダーを目指します。 特にポイントになるのが「リーダー企業の弱いところを崩すか」「リーダー企業がカバーできない小規模な市場でリーダーになれる」ようにターゲティング広告を打つことです。例えば、花王の「ヘルシア緑茶」は、「リーダー企業の弱いところを崩すか」「リーダー企業がカバーできない小規模な市場でリーダーになれる」ようにターゲティング広告を打ち、ポジショニングに成功。
もともと、緑茶業界は「お~いお茶」や「伊右衛門」、「生茶」など数多くの商品があり新規参入は難しいと考えられていました。
しかし、花王はそれらの既存商品が若者向けであると分析、「肥満に悩む中年男性」をターゲットにして「コンテンツターゲティング」と「リターゲティング」を打ったのです。
その結果、「ヘルシア緑茶」は独自のポジショニングによって成功を果たしました。
ターゲティングの成功事例
マーケティング用語としてターゲティングの成功事例
選択的専門化戦略
リクルートは、M&Aなどで多様な企業や製品を取り込んだコングロマリット的企業が採用する選択的専門化戦略をとってターゲティングに成功。新卒就活時には「リクナビ」利用した多くの人は、ライフステージごとに「転職活動」や「結婚」あるいは「住宅購入」などすることになるが、リクルートはそのライフステージごとに「リクナビキャリア」「ゼクシィ」「SUUMO」などのサイトを用意してLTV(顧客生涯価値最大化)を実現しています。
単一セグメント集中戦略
単一セグメントへ企業資産を集中投入するターゲティングの成功事例。・都市部のビジネスワーカーにターゲットを絞った「スターバックス」
・散髪の時間とコストの縮小を望む人にターゲットを絞った「QBハウス」
・手頃な質とコスト、どちらも望むにターゲットを絞った「無印良品」
・ターゲットを海で遊ぶ男性から都会の女子高生に変更したコスメ商品「シーブリーズ」
・高齢者イメージの強かった電動歯ブラシのターゲットを女性に変更して成功したパナソニック「ポケットドルツ」
・サラリーマン狙いの「吉野家」と異なるターゲット「郊外のファミリー」に絞った「すき家」
広告用語としてのターゲティングの成功事例
オーディエンスターゲティング広告の成功事例
・購入の可能性が高いFacebookユーザーにのみ広告を配信した「オイシックス」Facebookは実名登録が必要で、社会人の多いSNSなので、ライフステージの高いオーディエンスターゲティング広告を打てるメリットを活かし成功。
・国際大会の国内開催で盛り上がっていたラグビーについて知りたいと感じているInstagramユーザーをターゲットに絞った「日本航空」
デバイスターゲティング広告の成功事例
・Facebook広告をモバイルデバイス向けに最適化した健康食品・健康用品の「京都やまちや」コンテンツターゲティングとリターゲティング広告の成功事例
・肥満に悩む中年男性をターゲットにダイエットコンテンツサイトでの広告及びダイエット関連検索へのリターゲティング広告で成功した「ヘルシア緑茶」ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム